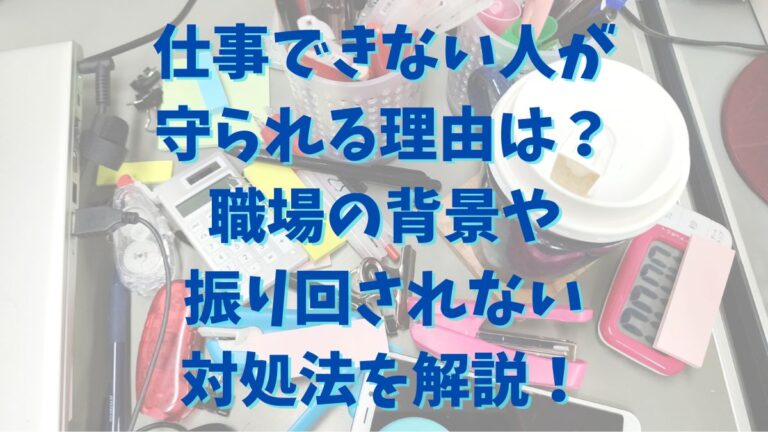仕事できない人が守られる理由について疑問を持ったことはありませんか。
職場では、能力が高い人が報われるとは限らず、逆にできない人が守られている場面を目にすることがあります。
この記事では、なぜそのような状況が起きるのか、背景にある心理や制度、そしてその影響について詳しく解説します。
さらに、守られる人と守られない人の違いや、振り回されないための具体的な対処法も紹介します。
読み終えたときには、職場でのモヤモヤが整理され、より冷静に人間関係や働き方を考えられるようになりますよ。
仕事できない人が守られる理由

仕事できない人が守られる理由について解説します。
それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
上司や会社が責任を取るため
仕事できない人が守られる背景のひとつには、上司や会社が責任を取る必要があるという事情があります。
たとえば、部下の失敗は最終的に上司の責任になります。そのため、たとえ本人がミスを繰り返しても、上司がかばうように立ち回ることがあるのです。
また、会社の立場から見れば「解雇する」という選択肢は簡単ではありません。雇用契約や人員配置のバランスもあるため、守るしかないケースが出てきます。
つまり、組織を円滑に動かすために、できない人を守ることが一種のリスク回避になっているということです。
この仕組みは理不尽に見えることも多いですが、現実には企業防衛の一環として存在しています。
人間関係やコネが影響する
職場で守られる人と守られない人の差を生む大きな要因に、人間関係やコネがあります。
上司と仲が良い人や、社内で影響力のある人とつながっている人は、不思議と守られる傾向があります。
これは公平さを欠くように思えるかもしれませんが、職場は人間関係で成り立っている場でもあります。結果として、できるかどうかよりも「誰に気に入られているか」が守られるかどうかを左右することもあります。
裏を返せば、日頃の態度や人付き合いが自分を守ってくれる盾になることもあるということです。
仕事の成果だけでは評価が決まらないという現実を、多くの人は肌で感じているでしょう。
法律や労働環境の制約
法律や労働環境の制約も、仕事できない人が守られる理由のひとつです。
日本の労働基準法は従業員を強く保護しています。そのため「仕事ができない」という理由だけでは、簡単に解雇することはできません。
加えて、社会的に「働き続ける権利」が尊重される流れもあります。そのため、会社は配置転換や教育研修などの形で守る姿勢を取らざるを得ないのです。
労働組合の影響や、ハラスメント防止の観点も大きく関わっています。むしろ解雇したことで訴訟に発展するリスクの方が、会社にとっては負担になります。
つまり、制度的に守られてしまう構造があるため、できない人でも職場に居続けられるのです。
組織の空気を壊さないため
職場の空気を壊さないようにするために、仕事できない人が守られる場合もあります。
もし露骨に「あなたはできないから外れてください」と伝えると、周囲の雰囲気も悪くなります。場合によっては職場全体の人間関係にヒビが入ってしまうこともあります。
上司からすれば、多少の非効率があったとしても、チーム全体の和を乱さないことの方が重要と考えるケースがあるのです。
日本社会では「和を以て貴しとなす」という価値観が今も色濃く残っています。そのため、個人の能力よりも空気を大切にする傾向があるのです。
この空気の配慮が、できない人を守る結果につながっているとも言えるでしょう。
同情や期待があるから
仕事できない人が守られる最後の理由は、同情や期待があるからです。
「まだ新人だから」「伸びしろがあるかもしれない」といった気持ちが、周囲を甘くさせます。
また、困っている姿を見て放っておけないという心理も働きます。特に人情に厚い上司や同僚がいる場合、その人をかばってあげることが多いのです。
一方で、期待が裏切られ続ければ守られる期間も短くなります。つまり「守られるのは今だけ」という場合も少なくありません。
守られる背景には、人としての情や希望が反映されているということです。
仕事できない人が守られることで起きる問題

仕事できない人が守られることで起きる問題について解説します。
では、それぞれを詳しく見ていきましょう。
職場全体のモチベーション低下
仕事できない人が守られると、周囲のモチベーションが大きく低下します。
なぜなら、頑張って成果を出しても報われず、むしろできない人が優遇されているように感じてしまうからです。
特に、同じチームで働く場合はその影響が顕著です。周りが必死にフォローしているのに、本人が改善されず守られているとなれば「なんで自分だけ苦労しているのか」と不満が募ります。
この不満は表面的には見えにくいですが、徐々にやる気の低下や生産性の低下につながります。
つまり、組織の中に「やってもやらなくても同じ」という空気が広がってしまうのです。
優秀な人材の離職リスク
守られる人がいると、そのしわ寄せが優秀な人材に集中します。
本来なら平等に分担すべき業務が、一部の人に偏ってしまうからです。結果として、優秀な人材ほど「ここで頑張っても無駄だ」と感じて転職を考えるようになります。
特に今の時代は働き手が会社を選ぶ傾向が強くなっています。市場価値の高い人材ほど、より良い環境を求めて離れていきやすいのです。
つまり、守られる人を庇うことは、組織にとって大切な人材を失うリスクを増やすことにもつながります。
短期的には波風が立たなくても、長期的には大きな損失になるのです。
不公平感が広がる
仕事できない人が守られている光景は、多くの人に「不公平だ」と感じさせます。
評価基準が曖昧になり「頑張っても意味がない」という空気が定着すると、組織全体の公平性が崩れます。
人間は平等であることに敏感です。特に職場は、給与や評価と直結しているため、不公平が積み重なると大きな不満になります。
また、この不公平感は単なる不満にとどまらず、チーム内の協力関係にも悪影響を及ぼします。
「どうせ守られるんでしょ」という皮肉な見方が広がれば、協力しようという意欲すら薄れてしまうのです。
組織の成長が停滞する
仕事できない人が守られることで、組織の成長スピードが停滞します。
本来なら効率的に進むはずの業務が、フォローや調整に時間を奪われるからです。
さらに「守られる人がいるのだから、自分も頑張らなくてもいいや」と考える人が出てくると、全体的な基準が下がります。
組織として新しいチャレンジに踏み出すエネルギーも失われ、保守的で停滞した雰囲気に陥ります。
つまり、短期的には円滑に見えても、長期的には成長を止めてしまう危険性を抱えているのです。
仕事できなくて守られる人と守られない人の違い

仕事できなくて守られる人と守られない人の違いについて解説します。
守られる人とそうでない人の違いはとても微妙ですが、職場の現実を知るために重要です。
信頼関係の有無
まず大きな違いは、信頼関係の有無です。
仕事ができなくても、上司や同僚と良好な信頼関係を築いている人は、守られる傾向があります。
逆に、スキルが多少あっても信頼されていなければ、問題が起きたときに庇われません。
信頼は日々の行動の積み重ねで作られます。小さな報告や相談を怠らず、誠実に取り組む姿勢を見せているかどうかが鍵です。
つまり「できるかどうか」よりも「信じてもらえるかどうか」が、守られる人の条件になるのです。
コミュニケーション力の差
次に大きな違いは、コミュニケーション力です。
同じように成果が出ていなくても、自分の状況を素直に伝えられる人は「助けてあげよう」と思われやすいです。
一方で、黙り込んでしまう人や、責任を他人に押し付ける人は、周囲からの信頼を失います。
つまり、できないことを正直に共有できる人ほど、守られる可能性が高くなるのです。
仕事そのものの能力よりも「人とつながる力」が評価に影響しているとも言えます。
性格や態度の印象
性格や態度の印象も、守られるかどうかを大きく分けます。
同じように仕事ができなくても、明るく前向きな人や努力を見せる人は応援されやすいです。
反対に、言い訳ばかりしたり不満を口にする人は、守るどころか距離を置かれてしまいます。
職場では「一緒に働きたい人」が自然と選ばれるため、態度の良し悪しが守られるかどうかを決める大きなポイントになります。
つまり「好かれるか嫌われるか」という印象の差が、そのまま扱いの差につながるのです。
上司との相性や評価軸
最後に、上司との相性や評価軸の違いも大きな要因です。
上司によって評価基準は異なります。スピードを重視する人もいれば、丁寧さを評価する人もいます。
つまり、仕事できないとされている人も、評価軸によっては「守る価値がある」と判断されることがあります。
また、人間的な相性も無視できません。同じ趣味を持っていたり、考え方が似ているだけで、守られる可能性は高くなります。
公平でないように思えますが、現実の職場は人間関係と相性で動いている部分が大きいのです。
仕事できない人を守る職場の背景

仕事できない人を守る職場の背景について解説します。
なぜ仕事できない人が守られるのか、その背景には組織の心理や文化的な要素が深く関わっています。
和を乱さない文化
日本の職場文化に強く根付いているのが「和を大切にする」という考え方です。
仕事ができない人を露骨に排除すると、チーム全体の空気が悪くなる恐れがあります。
そのため、非効率であっても守っておいた方が組織が円滑に回ると判断されるのです。
特に日本社会では「成果よりも協調性」を重んじる傾向が強く、和を乱すことは大きなマイナスと見なされます。
つまり、個人の能力不足をカバーしてでも、平穏な雰囲気を維持することが優先されるわけです。
責任の押し付け合い
職場では、誰もが余計な責任を背負いたくないという心理が働きます。
仕事できない人を正面から指摘して改善を促すことは、上司や同僚にとって大きな負担になります。
その結果、「波風を立てるくらいなら守っておこう」という選択がなされるのです。
特に大企業では組織が大きい分、責任の所在が不明確になりやすく、問題を見て見ぬふりする傾向が強くなります。
つまり、守るというよりは「責任を避けるための妥協」が背景にあるのです。
評価制度の曖昧さ
評価制度が明確でない職場では、仕事できない人が守られやすくなります。
なぜなら「何をもって仕事ができるのか」がはっきりしていないため、能力不足を理由に切り捨てにくいからです。
例えば、スピードを重視する部署と、正確さを重視する部署では評価の基準がまったく異なります。
この曖昧さが、守られる人を生み出してしまうのです。
さらに、評価が数値化されていない職場では、上司の主観が強く働くため「守るかどうか」が恣意的に決まるケースもあります。
メンタルヘルスへの配慮
近年、職場ではメンタルヘルスへの配慮が強く求められるようになっています。
そのため、本人に厳しい指摘をすると精神的に追い込んでしまうリスクがあり、むしろ守る方向に動くケースが増えています。
特に過労やストレスが社会問題になっている現代では、組織として「守る」ことが安全策になるのです。
また、ハラスメント防止の観点からも、過度な叱責は避けられる傾向があります。
結果として、改善が見られないまま守られ続ける状況が生まれてしまうのです。
仕事できない人に振り回されないための対処法

仕事できない人に振り回されないための対処法について解説します。
では、具体的にどのように対処すべきかを見ていきましょう。
自分の役割を明確にする
まず大切なのは、自分の役割をしっかりと明確にすることです。
仕事できない人のフォローばかりしていると、本来自分が担うべき業務が疎かになってしまいます。
そこで、自分が責任を持つ範囲をはっきり示し、それ以外の部分は必要に応じて上司に判断を仰ぐ姿勢が有効です。
役割を明確にすることで「これは自分の責任ではない」と線引きができ、振り回されにくくなります。
チームで働く以上、助け合いは大切ですが、自分が犠牲になる必要はないという意識を持つことが大事です。
冷静に境界線を引く
仕事できない人に振り回されないためには、冷静に境界線を引くことも欠かせません。
相手が困っているとつい助けてしまいたくなりますが、無制限にフォローしていると依存されるだけです。
「ここまでは協力するけれど、それ以上は自分でやってください」という態度を持つことが必要です。
冷静に境界を引くことで、自分のリソースを守ることができます。
感情に流されずに線を引けるかどうかが、長期的に職場で健全に働き続けるためのポイントです。
上司へ適切に相談する
どうしても振り回されてしまう場合は、上司へ適切に相談することが重要です。
ただし、単に「迷惑です」と伝えるのではなく、具体的な事実を整理して伝えることが大切です。
例えば「この業務に○時間かかり、自分の本来の業務に支障が出ています」と数字を交えて報告すると、上司も対応を検討しやすくなります。
上司に共有することで、フォロー体制や人員配置を見直すきっかけになることもあります。
問題を一人で抱え込まず、組織として解決に動いてもらうことが効果的です。
感情的にならずに対応する
仕事できない人にイライラすることは自然な反応ですが、感情的に接すると逆効果です。
強い口調で責めると相手が反発したり、逆に萎縮してさらに仕事ができなくなる可能性もあります。
冷静かつ客観的に対応することを意識することで、自分自身の精神的な消耗も減らせます。
また、職場では「感情的にならない人」が信頼されやすいので、自分の評価を守る意味でも冷静さは大切です。
感情に流されず事実ベースで対応することが、結局は自分を守ることにつながります。
自分のスキルを磨いて差別化する
最後に、自分のスキルを磨いて差別化することも有効です。
仕事できない人が守られている状況に不満を持っても、すぐに変えられるものではありません。
そのため、自分自身の市場価値を高め、どこでも通用する力を身につける方が建設的です。
専門スキルを磨いたり、新しい知識を取り入れたりすることで、評価が高まり「振り回される側」から抜け出すことができます。
長期的には、環境を変える選択肢も持てるようになるので、余裕を持って働けるようになるのです。
まとめ|仕事できない人守られる背景と向き合い方
| 仕事できない人が守られる理由 |
|---|
| 上司や会社が責任を取るため |
| 人間関係やコネが影響する |
| 法律や労働環境の制約 |
| 組織の空気を壊さないため |
| 同情や期待があるから |
仕事できない人が守られる背景には、会社のリスク回避や人間関係の影響、法律や文化的な事情があります。
一見理不尽に見える仕組みですが、組織が安定して動くために存在している面もあるのです。
ただし、守られることで職場に不公平感やモチベーション低下が広がるのも事実です。
大切なのは、自分の役割を明確にし、冷静に境界線を引きながら振り回されないようにすることです。
同時に、自分のスキルを磨くことで、どんな環境でも通用する力を身につけていけます。
不満や違和感を抱えながら働くのではなく、知識と工夫で乗り越える視点を持ちましょう。
関連情報として、厚生労働省が公開している 職場におけるハラスメント対策 も参考になります。