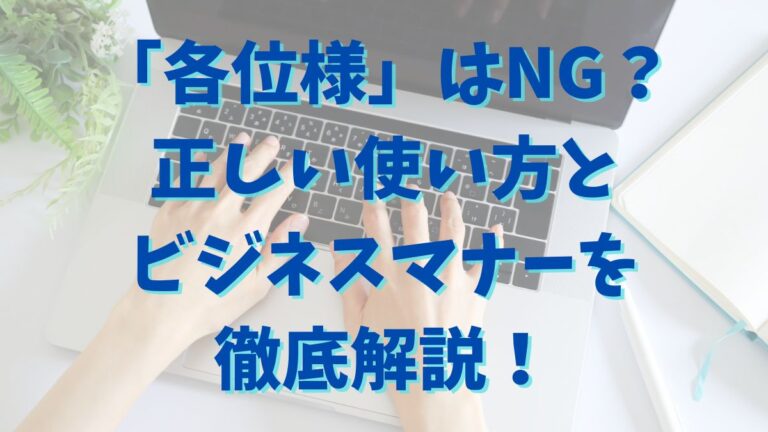「各位様」と書いてしまって不安になった経験はありませんか?
実は、「各位様」は敬語を重ねた二重敬語となり、ビジネスマナーとしてNGとされる表現です。
この記事では、なぜNGなのか、正しい使い方や言い換え表現、間違えやすい背景まで分かりやすく解説します。
もう恥をかかないために、正しい敬語表現を身につけていきましょう。
各位に様をつけることがNGの理由

各位に様をつけることがなぜ間違いなのかについて解説します。
それでは詳しく見ていきます。
各位の意味と使い方
各位という言葉は、相手が複数人いる場合に「皆さま」や「みなさん」と同じような意味で使われます。
ビジネスの現場では「関係者各位」「お取引先各位」「社員各位」といった形で書かれることが多いです。
「各位」自体がすでに十分に丁寧な敬称になっており、そのあとにさらに敬称を加える必要はありません。
つまり、各位は相手に敬意を込めて複数人に向けて使う言葉です。
一人ひとりをまとめて丁寧に呼びかける意味で、正式な文書や案内状、社内メールでも頻繁に使われています。
様をつけると二重敬語になる理由
「様」は日本語の敬称の中でも最も一般的に使われるもののひとつです。
「各位」はそれ自体に敬意が含まれているので、「各位様」とすると敬意が重複してしまいます。
日本語のビジネスマナーでは、同じ意味で敬意を重ねて表現する「二重敬語」は原則としてNGとされています。
たとえば、「ご覧になられる」「お召し上がりになられる」といった二重敬語がよく指摘されるのと同じ感覚です。
「各位様」は「皆さま様」と同じくらい不自然で、マナー的にも間違いとされているのです。
ビジネスマナーとしてのNG例
ビジネスメールや社内外の案内文書などで「各位様」と記載するケースが時々見受けられます。
しかし、これは公式な場では誤った日本語表現として指摘されることが多いです。
実際に大手企業のビジネスマナー研修や各種ビジネスマナー書籍でも、「各位様」はNGワードとして例示されています。
顧客や上司、取引先に対して誤って「各位様」と書いてしまうと、日本語の使い方やマナーに疎いと思われることもあるので注意が必要です。
大切な連絡や案内こそ、正しい表現で信頼を損なわないようにしましょう。
間違いに気づかず使っているケース
「各位様」はビジネスの現場で見かけることが少なくありませんが、その多くが間違いに気づかず使ってしまっているケースです。
テンプレートや前例を真似してしまい、気づかないうちに誤用が広がっている場合もあります。
とくに新入社員や、転職したばかりの方は前の会社の慣習をそのまま持ち込んでしまうことがあるため要注意です。
もし間違いに気づいたら、次回から正しい使い方に直すよう心がけましょう。
ビジネスメールは細かい部分のマナーが意外と相手に伝わりますので、正しい日本語を意識することが大切です。
各位の正しい表現と使い分け

各位の正しい表現と使い分けについて解説します。
それぞれの場面ごとにポイントを見ていきましょう。
社内メールでの正しい使い方
社内メールでは「各位」という表現をシンプルに使うことが最も一般的です。
たとえば、「営業部各位」「関係者各位」「社員各位」などのように、宛名として文頭に配置します。
ここに「様」や「殿」などの敬称を重ねることは不要であり、むしろ過剰な敬語となってしまいます。
多くの大企業や官公庁のメールマナーでも、社内の複数人宛てには「各位」を使うだけで十分とされています。
自信を持って「各位」と記載し、安心してやり取りしましょう。
社外メールでの表現
社外メールの場合、「各位」だけではややカジュアルに見えてしまうと感じる方もいるかもしれません。
ただし、基本的には「ご担当者各位」「お取引先各位」などが標準的な表現です。
相手との関係性や状況によっては、「ご担当者さま」や「〇〇株式会社御中」のように、より丁寧な敬称に切り替えるのも適切です。
複数の取引先に一斉送信する場合は「各位」を使うことで失礼にはあたりません。
迷ったときは「各位」を選んでおけば、相手に失礼なく情報を伝えることができます。
敬称を使う場面の例
「様」や「殿」などの敬称は、基本的に個別の名前や役職に対して使うものです。
たとえば、「山田様」「営業部長殿」など、特定の一人に向けて敬意を示す際に使われます。
一方で「各位」はグループ全体に敬意を払うための言葉なので、ここに「様」を重ねると違和感が生まれます。
「皆様」や「ご担当者様」など、人数が明確でない場合には「様」をつけても問題ありません。
用途ごとに表現を使い分けることが、ビジネスメールでは大切です。
各位を使わずに丁寧に伝える方法
「各位」を使うのが適切でないと感じる場合や、より丁寧に伝えたいときには、「みなさま」「ご関係者さま」などの言い回しも使えます。
たとえば、イベントの案内文やお礼状では「ご出席いただいた皆様へ」などが好まれることもあります。
また、「御中」や「ご担当者さま」など、相手の立場や人数に応じた表現を選ぶことで、相手により丁寧な印象を与えることができます。
どの表現も日本語として違和感がないか、一度声に出して確認してみるのもおすすめです。
状況や相手に合わせた書き方を心がけることで、より好印象なメールが書けます。
各位に様をつけることが生まれた背景
各位に様をつけることが生まれた背景について解説します。
それぞれの背景について詳しく見ていきましょう。
日本語の敬語表現の変遷
日本語の敬語は、時代ごとに変化しながら現代に受け継がれてきました。
かつては身分や立場に応じて細かく使い分けられていましたが、現代ではビジネスマナーとして統一したルールが求められるようになりました。
その過程で、敬語の重ねがけや、より丁寧さを追求する文化が生まれました。
一方で、過剰な敬語はかえって不自然になり、正しい敬語表現が重視されるようになっています。
「各位様」のような二重敬語がNGとされるのは、こうした日本語敬語の歴史的な変遷も影響しています。
ビジネス現場での慣用ミス
ビジネスの現場では、先輩や上司のメール、過去の社内文書を参考に文章を作ることがよくあります。
そのため、誰かが一度「各位様」と書いたメールがそのままテンプレート化し、ミスが連鎖して広まることもあります。
特に新入社員や異動直後の社員は、正しい敬語の知識がないまま前例を踏襲してしまいがちです。
一度慣習化した表現はなかなか修正されず、会社全体に広がってしまうことがあります。
こうした背景が「各位様つけるNG」が繰り返される要因の一つです。
メール文化の影響
インターネットやメールの普及によって、ビジネスで文章を書く機会が爆発的に増えました。
一斉送信やテンプレートの利用が当たり前になり、個別の相手に敬称をつける感覚が薄れてきた面もあります。
特に、複数人宛てのメールで「様」や「殿」などの敬称をつい加えたくなる心理も働きやすくなっています。
また、丁寧すぎる表現が好まれる傾向もあり、知らず知らずのうちに二重敬語を使ってしまう人も少なくありません。
こうしたメール文化の広がりが、「各位様」という表現の誤用を後押ししていると言えるでしょう。
各位に様をつけることを避けるポイント

各位に様をつけることを避けるポイントについて解説します。
ビジネスメールや案内文で失礼のない表現を身につけましょう。
テンプレートを見直す方法
会社や部署で長く使われているメールテンプレートには、誤った表現がそのまま残っている場合があります。
一度テンプレートの内容を見直して、「各位様」などのNG表現が含まれていないかチェックしましょう。
必要に応じて「社員各位」「関係者各位」など、正しい表現へ修正するのが大切です。
みんなで使うフォーマットこそ、間違いのない内容にアップデートしましょう。
小さな修正でも職場全体のマナー意識が大きく変わります。
メールの冒頭文の注意点
メールの冒頭に「各位様」や「各位殿」などと記載してしまうことは、意外とよくあります。
「様」「殿」はつけずに「各位」と書くだけで、十分に丁寧な呼びかけになります。
他の敬称をつけたくなった時は、一度立ち止まって文章を声に出して読んでみましょう。
違和感がある場合は、たいていNG表現です。
日頃から自然な言葉遣いを意識することで、間違いを減らせます。
迷った時の確認手段
メールや文書の表現に迷った時は、社内のビジネスマナー研修資料や公式ガイドラインを確認するのがおすすめです。
また、国語辞典やビジネス文書の解説書でも正しい使い方が紹介されています。
インターネット上の信頼できるマナーサイトや、上司や先輩に直接確認するのも良い方法です。
不安なまま送信せず、一度調べてみることでミスを未然に防げます。
習慣づけておくと、自分だけでなく周囲のマナー意識向上にもつながります。
例文集を活用するコツ
ビジネスメールや案内文の例文集は、正しい表現を身につけるための便利なツールです。
自分がよく使う場面の例文をチェックして、誤用がないか見直してみましょう。
たとえば「各位」の使い方が載っているビジネスマナー書籍や、社内資料を活用すると効果的です。
もし正しい例文が分からない場合は、複数の参考資料を見比べることも大切です。
正しい表現を繰り返し見て覚えることで、自然とマナーが身につきます。
正しいビジネスマナーのおすすめの学び方

正しいビジネスマナーのおすすめの学び方について解説します。
日頃からビジネスマナーを学び続けることで、表現ミスを防げます。
ビジネスマナー研修を受ける
新入社員や若手社員向けのビジネスマナー研修では、「各位様」のようなNG表現が必ずと言っていいほど取り上げられます。
体系的にビジネスマナーを学ぶことで、なぜNGなのか、どう改善するのかをしっかり理解できます。
一度でも実践的な研修に参加することで、自分の中に正しい日本語表現が根付くようになります。
社内外のマナー研修やeラーニング講座も積極的に活用しましょう。
定期的な振り返りも大切です。
社内教育やチェックリストの活用
自分一人だけでなく、職場全体で正しいマナーを共有する仕組みも重要です。
社内でメール表現のチェックリストを作成したり、誤りやすいポイントを共有する時間を設けると効果的です。
グループ単位でフィードバックし合う文化を作ることで、自然とマナーが身についていきます。
わからない時はお互いに確認し合い、改善のきっかけにしましょう。
小さな工夫がミス防止につながります。
おすすめ書籍やサイトで学ぶ
ビジネスマナー関連の書籍や、信頼できるマナーサイトも、学習の強い味方です。
実際のメール例文や解説を読みながら、正しい「各位」の使い方を身につけることができます。
総務省や文化庁などの公式サイトや、大手企業が発信するマナー記事は特に参考になります。
最新の情報や時代に合った表現も日々アップデートされているので、定期的にチェックしておくと安心です。
新しい知識をどんどん取り入れていきましょう。
日常業務で意識する工夫
毎日のメールや社内文書を書くときに「この表現で正しいかな?」と一度考える習慣が大切です。
繰り返し意識して使うことで、自然と誤用を防げるようになります。
周囲から指摘されたら素直に受け止めて修正し、自分の成長につなげていきましょう。
また、分からないときは恥ずかしがらずにすぐ調べることが大事です。
日々の積み重ねが、自信を持ったビジネスコミュニケーションにつながります。
まとめ|各位に様をつけることがNGの理由と正しい使い方を押さえよう
| 各位に様つけることがNGの理由 |
|---|
| 各位の意味と使い方 |
| 様をつけると二重敬語になる理由 |
| ビジネスマナーとしてのNG例 |
| 間違いに気づかず使っているケース |
「各位様」という表現は、一見丁寧に見えますが、実際は敬語が重なった二重敬語です。
ビジネスシーンでは「各位」自体がすでに敬意を含むため、「様」をつけると過剰表現になります。
社内外問わず、正しい言葉づかいを心がけることで、信頼感のあるやり取りができるようになります。
今回紹介した例やポイントを参考に、日常業務でも正しい日本語を意識していきましょう。
公式な場面で恥をかかないためにも、言葉選びには慎重さが求められます。