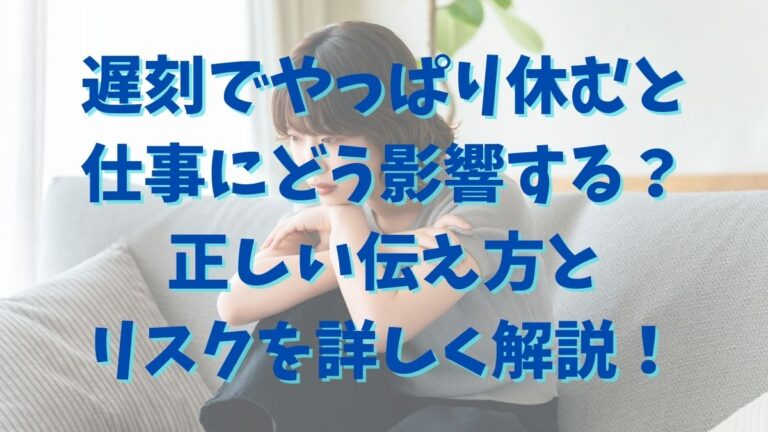「遅刻しそうだからやっぱり休む」と仕事を休んだ経験はありませんか。
そのときは気まずさを避けられても、実は会社や上司からの評価に大きく影響することがあります。
この記事では、遅刻と欠勤の違い、休むときの正しい伝え方、実際に使えるフレーズ、そして繰り返すことで生じるリスクについて詳しく解説します。
読んだ後には、遅刻や欠勤にどう向き合えばよいのかがはっきり分かるようになりますよ。
遅刻でやっぱり休むと仕事に影響する?

遅刻でやっぱり休むと仕事に影響するのかについて解説します。
それでは順番に説明していきますね。
遅刻と欠勤の違い
遅刻と欠勤は似ているようで、会社に与える影響や評価のされ方が大きく異なります。
遅刻は勤務時間に間に合わなかった状態を指し、多少の遅れであれば業務に戻ってその日のタスクを進めることが可能です。
一方で欠勤は丸一日勤務を放棄する行為となり、その日の仕事がまったく進まなくなります。
例えば、午前中に大事な打ち合わせが予定されていた場合、遅刻であれば後半から参加できる可能性がありますが、欠勤すると完全に不在になります。
この違いはチーム全体の進行に直接響くため、会社としては欠勤の方を重く受け止める傾向があります。
実際の就業規則でも「遅刻」「早退」「欠勤」は別々に扱われ、欠勤の回数が多い方が人事評価や査定に大きく影響することが一般的です。
そのため「少しでも出社できるなら遅刻してでも行く」ことが、誠実さとして評価されやすいケースが多いのです。
休むと伝える心理的背景
遅刻しそうになったときに「やっぱり休む」と判断する背景には、心理的な要因が強く関わっています。
一つは「遅刻をして叱られるくらいなら休んでしまった方が楽」という逃避の気持ちです。
もう一つは「途中から行っても迷惑をかけるかもしれない」という気遣いの気持ちです。
特に真面目な人ほど「遅刻する自分が職場に現れることで悪い印象を残すのではないか」と考えてしまい、結果的に休むことを選んでしまうのです。
ただし、この判断は必ずしも正解ではありません。短期的には叱責や気まずさを避けられますが、長期的には「責任感が薄い」と思われるリスクがあります。
この心理は理解できるものですが、社会人としては「出社してできることをやる」という姿勢を見せた方がプラスに働くことが多いのです。
社会人としての評価への影響
遅刻と欠勤では、社会人としての評価に大きな差が生じます。
例えば、月に数回の遅刻があったとしても、その日の業務をある程度こなせば「不注意」や「生活習慣の乱れ」といった評価で済む場合があります。
しかし欠勤を繰り返すと「責任感がない」「仕事を投げ出す」といった根本的な評価に直結しやすくなります。
特にチームで進める仕事の場合、1人が突然欠勤すると残りのメンバーに大きな負担がかかり、信頼を損なうことにつながります。
さらに、欠勤が増えると人事評価に悪影響を及ぼし、昇進やボーナス査定に響くことも珍しくありません。
つまり「遅刻はマイナスだが欠勤はもっと大きなマイナス」と捉えられるのが一般的な職場の空気です。
会社や上司の受け止め方
会社や上司が「遅刻」と「やっぱり休む」をどう受け止めるかは、その場の状況や文化によって変わります。
厳格な会社であれば「どちらもマイナス」と評価されますが、それでも遅刻して出社する姿勢の方が誠実さとして受け取られることが多いです。
一方、体調不良や家庭の事情など正当な理由がある場合は、無理に遅刻して出社するより休んだ方が良いと判断されるケースもあります。
つまり大切なのは「なぜ遅刻しそうなのか」「なぜ休むのか」を誠実に説明することです。
説明がしっかりしていれば、一時的なマイナスはあっても長期的な信頼を失うことは避けられます。
逆に、理由をあいまいにしてしまうと「サボり」や「甘え」と受け止められてしまい、評価を大きく下げてしまう可能性があります。
遅刻より休むを選んだときの伝え方

遅刻より休むを選んだときの伝え方について解説します。
それぞれのシーンごとに詳しく見ていきましょう。
電話で伝えるときの注意点
遅刻ではなく休むと判断した場合、もっとも誠実に伝えられる手段は電話です。
電話は相手の声を直接聞けるため、誠意や緊急性を伝えやすい特徴があります。
ポイントは出社時間前に必ず連絡を入れることです。始業後に連絡すると「サボりではないか」と疑われやすくなります。
また、上司本人に直接伝えることが理想ですが、不在の場合は事務担当や同僚に伝え、必ず「折り返しをお願いできますか」と一言添えると丁寧です。
内容は「理由」「謝罪」「本日の欠勤を伝える」の三点を簡潔にまとめましょう。
例:「おはようございます。営業部の〇〇です。本日、体調不良で出社が難しいため、お休みをいただければと思います。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。」
メールやチャットでの伝え方
どうしても電話ができない場合は、メールやチャットで伝えることになります。
このときに注意すべきは、件名と冒頭で要件を明確に示すことです。
例えば、件名を「本日欠勤のご連絡(営業部〇〇)」とすれば、受け取った相手が一目で状況を理解できます。
本文では「理由」「欠勤の事実」「謝罪」を簡潔に伝えます。文章が長いと読み手に負担をかけるので、2〜3行でまとめるのが理想です。
また、チャットであっても敬語を崩さず、丁寧な文面を意識しましょう。
カジュアルなツールであっても、ビジネス上は正式な連絡手段のひとつとして扱われるためです。
正直さと説明のバランス
休む理由を伝えるとき、どこまで正直に話すべきかは悩ましいポイントです。
基本的には「体調不良」「家庭の事情」「交通機関の遅延」など、相手が理解しやすい理由を簡潔に伝えるのがベストです。
例えば「寝坊しました」と正直に伝えると、誠実ではありますが印象は悪くなります。
一方で、理由をあいまいにしすぎると「隠しているのでは」と不信感を招くリスクがあります。
そこで重要なのは「正直さ」と「印象」のバランスをとることです。
体調不良が理由なら「無理して出勤して悪化しても迷惑になるので休ませていただきます」と添えると理解されやすくなります。
謝罪の仕方と印象の残し方
欠勤を伝えるときは必ず謝罪を含めましょう。
ただし、長々と謝罪の言葉を重ねる必要はありません。簡潔に「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と一言添えれば十分です。
大切なのは、翌日に出社したときに改めて直接謝ることです。
その場で「昨日は急にお休みをいただき申し訳ありませんでした」と挨拶をすれば、誠実さが伝わり、マイナスイメージを最小限にできます。
また、業務に遅れが出る場合は「〇〇の作業は明日必ず対応します」と前向きな言葉を添えると、信頼を保つことができます。
遅刻や休みの伝え方に役立つ実例
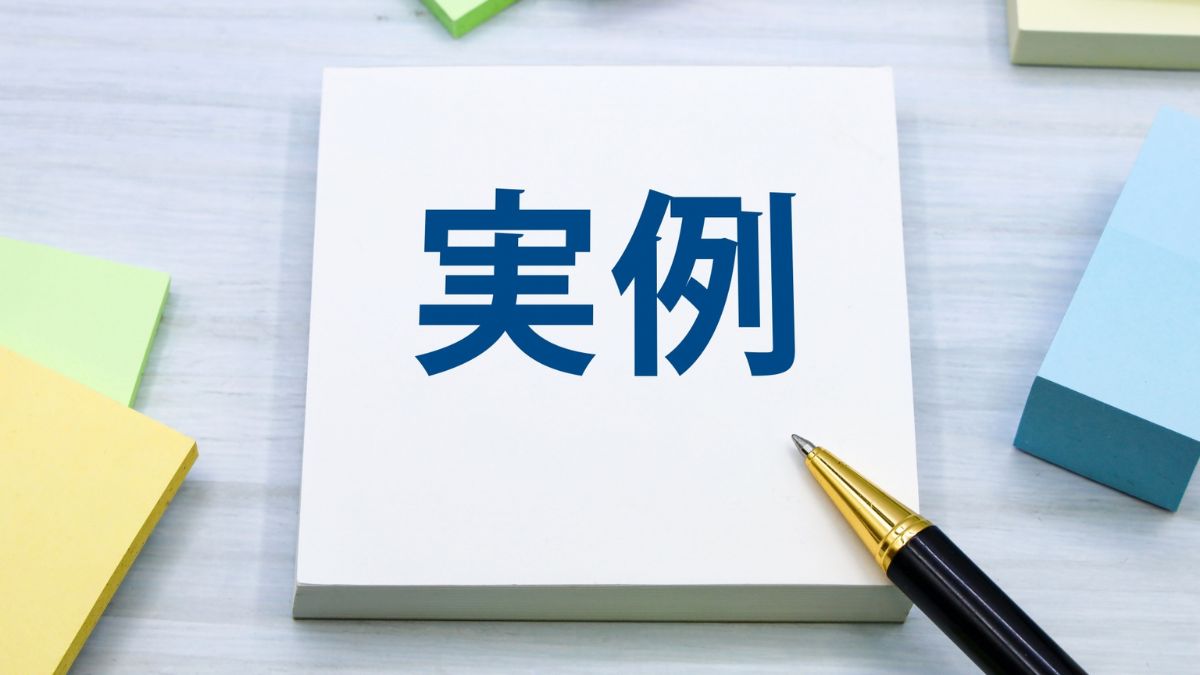
遅刻や休みの伝え方に役立つ実例を紹介します。
具体的なフレーズを準備しておくと、いざというときに落ち着いて連絡できます。
体調不良での伝え方
体調不良はもっとも一般的な欠勤理由です。そのため、シンプルで誠意のある伝え方を心がけましょう。
例文(電話の場合):「おはようございます。営業部の〇〇です。今朝から体調がすぐれず、出社が難しい状況です。本日はお休みをいただければと思います。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。」
例文(メールの場合):「お世話になっております。営業部の〇〇です。本日、体調不良のため欠勤させていただきます。急なご連絡となり申し訳ありません。よろしくお願いいたします。」
ポイントは「理由を具体的に言いすぎない」ことです。例えば「発熱で動けない」程度なら問題ありませんが、細かく症状を並べる必要はありません。
大切なのは「仕事ができない状態である」ことを簡潔に伝えることです。
交通トラブルでの伝え方
電車やバスの遅延、道路の渋滞などは誰にでも起こり得る理由です。
例文(電話の場合):「おはようございます。営業部の〇〇です。電車の大幅な遅延で出社が難しい状況です。本日はお休みをいただきたく、ご連絡いたしました。申し訳ありません。」
例文(メールの場合):「お世話になっております。営業部の〇〇です。本日、交通機関の遅延の影響で出社が困難なため欠勤いたします。急なご迷惑をおかけして申し訳ございません。」
ここで重要なのは「状況を簡潔に説明する」ことです。どの路線が止まっているのかなど、必要最低限の情報を伝えれば十分です。
無理に「代替手段を探しましたが…」と長々説明する必要はなく、要点を押さえることが印象を良くします。
家庭の事情での伝え方
家庭や育児の事情は理解されやすい一方、説明が難しいケースもあります。
例文(電話の場合):「おはようございます。営業部の〇〇です。本日、家庭の事情により出社が難しい状況です。急なお願いでご迷惑をおかけしますが、お休みをいただければと思います。」
例文(メールの場合):「お世話になっております。営業部の〇〇です。本日、家庭の事情により欠勤いたします。直前のご連絡となり申し訳ございません。よろしくお願いいたします。」
具体的に話す必要はありませんが、場合によっては「子どもの発熱」や「急な介護対応」といった理由を軽く添えると納得されやすくなります。
ただし、プライベートに踏み込みすぎない程度に留めることが大切です。
どうしても言いづらいときの無難な伝え方
寝坊や自己都合の場合は、正直に伝えると印象が悪くなることがあります。
このようなときは「体調不良」や「家庭の事情」といった無難な表現を使うことも一つの方法です。
例文(電話の場合):「おはようございます。営業部の〇〇です。本日、体調が優れず出社できない状況です。大変申し訳ありませんが、お休みをいただきたくご連絡いたしました。」
例文(メールの場合):「お世話になっております。営業部の〇〇です。本日、体調不良により欠勤させていただきます。急なご連絡でご迷惑をおかけし申し訳ございません。」
誤魔化すことに罪悪感を覚える人もいますが、社会的に受け入れられやすい言い方を選ぶことでトラブルを避けられます。
ただし、頻繁に使うと信頼を損なうため、やむを得ないときだけに限定することが大切です。
遅刻や欠勤を繰り返すことのリスク

遅刻や欠勤を繰り返すことのリスクについて解説します。
続けて見ていきましょう。
信用や評価の低下
遅刻や欠勤が一度や二度であれば「たまたま起きたこと」と受け止めてもらえる場合があります。
しかし、それが繰り返されると「信頼できない人」というレッテルが貼られてしまいます。
仕事はチームで進めることが多く、一人の不在や遅れが他のメンバーに直接的な負担をかけます。
そのため「頼りにできない人」と見なされると、重要な仕事を任せてもらえなくなります。
こうした評価の低下は目に見えにくいですが、長期的に大きな影響を与えます。
一度失った信用を取り戻すのは非常に時間がかかるため、遅刻や欠勤の繰り返しは避けるべきです。
契約社員やアルバイトへの影響
契約社員やアルバイトは正社員に比べてシビアに勤怠を評価されます。
シフト制の職場では、一人が欠けると即座に現場が回らなくなるため、欠勤は大きな問題とされます。
例えば飲食店や販売職では「欠勤が多い人」と判断された時点でシフトを減らされることがあります。
派遣や契約社員の場合は、契約更新に影響するケースも珍しくありません。
勤務態度が安定していないと見なされると「契約終了」となる可能性が高まります。
つまり、非正規雇用の場合は遅刻や欠勤の繰り返しが直接的に収入や雇用の継続に結びつくのです。
昇進や査定への影響
正社員であっても、遅刻や欠勤の多さは昇進や査定に大きく響きます。
人事評価では「成果」だけでなく「勤怠」も重視されます。
たとえ成果を出していたとしても、遅刻や欠勤が多ければ「組織を牽引する立場には不適切」と判断されることがあります。
昇進のチャンスを逃したり、ボーナスや昇給にマイナスの影響を受けることもあります。
さらに勤怠不良の履歴は人事システムに記録されることが多く、数年後の査定にも残る可能性があります。
つまり「今だけの問題」ではなく、将来のキャリア形成に影響を及ぼすリスクがあるのです。
最悪の場合の解雇リスク
遅刻や欠勤を繰り返すと、最悪の場合は解雇につながることもあります。
労働契約法では「解雇は客観的に合理的な理由を欠く場合は無効」とされていますが、勤怠不良は合理的な理由として認められることがあります。
特に「無断欠勤」を繰り返すと懲戒解雇の対象になるケースも少なくありません。
会社としては「業務を遂行する意思がない」と判断せざるを得なくなるためです。
また、解雇までいかなくても、降格や部署異動などのペナルティを課される場合があります。
遅刻や欠勤を繰り返すことで最終的に自分の職場を失うリスクがあることを忘れてはいけません。
まとめ|遅刻やっぱり休む仕事は信頼に直結する行動
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 遅刻と欠勤の違い | 遅刻は業務に参加できるが、欠勤は一日不在になるため影響が大きい |
| 休むと伝える心理的背景 | 叱責を避けたい気持ちや気遣いから「休む」を選びやすい |
| 社会人としての評価への影響 | 遅刻は軽いマイナス、欠勤は大きな信頼低下につながる |
| 会社や上司の受け止め方 | 誠実な説明があれば理解されるが、あいまいな理由は不信感を招く |
遅刻やっぱり休む仕事という判断は、気軽にしてしまうと信頼を大きく失う行動につながります。
欠勤は業務全体に影響し、繰り返せば昇進や査定、雇用契約に直結します。
大切なのは誠実な伝え方と、責任感を持って対応する姿勢です。
短期的に気まずさを避けるよりも、長期的な信頼を守ることが結果的に自分を助けます。