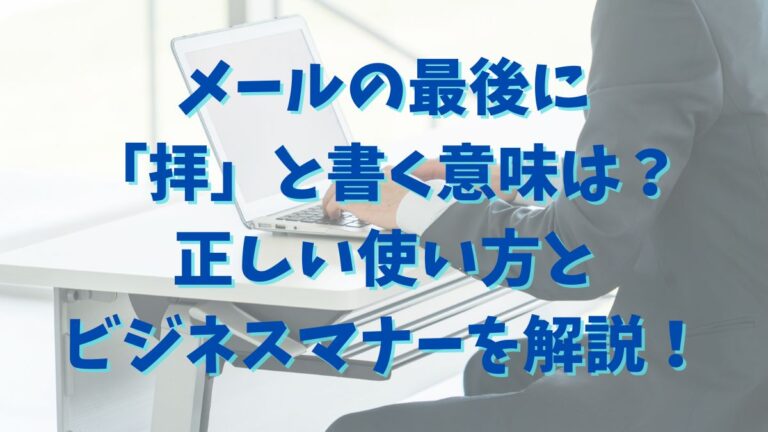メールの最後に「拝」と書かれているのを見て、どんな意味なのか気になったことはありませんか。
ビジネスメールや改まったやりとりの中で、ときどき見かける「拝」という結び言葉。
実は、これには日本ならではの深い意味や、相手への敬意が込められているのです。
でも、「どんな時に使えばいいの?」「失礼にならない?」と悩んでいる方も多いはず。
この記事では、「メール 最後 拝 意味」にまつわる疑問をわかりやすく解説。
使い方やマナー、よくあるトラブル例、さらに他の結び表現まで徹底的にまとめました。
正しい知識を身につけて、メールでしっかりと信頼感を伝えましょう。
最後まで読むことで、あなたの文章力もワンランクアップしますよ。
メールの最後に「拝」を使う意味と背景

メールの最後に「拝」を使う意味と背景について解説します。
それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。
「拝」の本来の意味
「拝」という言葉は、もともと「謹んで〜する」「深く敬意を表して〜する」という意味を持つ日本語です。
もともとは、神仏や目上の人に対して、頭を下げたり手を合わせる仕草から来ています。
「拝見」や「拝読」「拝聴」などの敬語にも使われ、相手への敬意や謙遜の気持ちを表す役割があります。
日常会話ではあまり使われない表現ですが、改まった文書や公的なやり取りでは現在でも使われることがあります。
メールの結びとして使う場合も、「あなたに敬意を持っています」「失礼のないようにしています」という気持ちが込められています。
メール結びで「拝」を使う理由
メールの最後に「拝」と書くのは、手紙文化から来ている日本独特のマナーの一つです。
手紙でいう「敬具」や「謹白」と同じような役割で、「ここで文章を締めくくります」「きちんとした態度でやり取りしています」というメッセージを伝えています。
自分の名前の後ろにつけることで、「私は敬意をもってこのメールを書きました」という意思表示になります。
昔は書状の最後によく使われていた表現ですが、現在でも格式を重んじる相手や場面では選ばれることがあります。
このような使い方は、特にビジネスや研究、官公庁関係、年配の方とのやり取りなどで見られます。
どんな業界・シーンで使われる?
「拝」をメールの結びとして使うのは、かなりフォーマルな場面や、古くからの慣習が残る業界で多いです。
たとえば大学の研究者同士、医療・教育現場、公的なやり取り、伝統的な業界などで使われることがよくあります。
IT企業や若いベンチャーではほとんど見かけませんが、年配の方や、昔ながらの会社では「拝」を見かけることも珍しくありません。
書面や封書では今も現役ですが、メールだと徐々に減っている傾向にあります。
ただ、格式や礼儀を重んじる相手や、改まったシーンでは今でも十分通用する表現です。
使い方の注意点
「拝」は便利ですが、乱用すると堅苦しくなったり、時代遅れな印象を持たれることもあります。
特に若い世代やカジュアルな関係の中では、使いすぎると「かしこまりすぎ」「距離を感じる」と思われがちです。
また、使い方を間違えると失礼にあたる場合もあるので注意が必要です。
たとえば「田中 拝 先生」など、敬称と組み合わせてしまうと逆に失礼です。
フォーマルなシーンでのみ、正しく使うようにしましょう。
メールで「拝」を使う時のマナー5選

メールで「拝」を使う時のマナー5選についてまとめます。
ひとつずつ詳しく紹介していきます。
①目上の人への使い方
「拝」は目上の人や、改まった相手にこそ適した表現です。
例えば、教授や役職者、取引先の担当者など、明確に上下関係がある相手に「田中 拝」と自分の名前の後ろに付けて締めくくります。
ビジネスや公的なメールでは、より丁寧な印象を与えるために使われることが多いです。
相手がフランクな雰囲気を好む場合や、カジュアルなやりとりが続いている時は、少し堅苦しくなりすぎることもあるので場面を選びましょう。
目上の人へ敬意を表す手段として、昔から日本で使われている表現です。
②ビジネスメールでのポイント
ビジネスメールで「拝」を使う場合は、使うタイミングと書き方に注意が必要です。
メールの本文の結びではなく、自分の署名部分、つまり「山田 拝」「佐藤 拝」のように、自分の名前の後に付けるのがマナーです。
本文の最後に「拝」だけを単独で書くと、何か違和感を持たれる場合もあります。
「拝」は伝統的な締めくくり表現であり、特に改まった第一報や公式な案内などの際に使うと効果的です。
日常的な社内メールやカジュアルなやりとりにはやや不向きです。
③親しい相手には使うべき?
親しい相手や友人とのメールでは、「拝」はほとんど使いません。
距離感が生まれてしまうため、普段のやりとりやフランクなメールには適していません。
また、同年代や年下、仲の良い同僚・友人などには「よろしくお願いします」や「ありがとうございます」など、シンプルな結び言葉の方が自然です。
「拝」はあくまで改まったシーンや、上下関係がある場合に限り使いましょう。
使う相手や場面をしっかり見極めて活用するのがポイントです。
④他の結び言葉との違い
「拝」は、日本語の中でも特にフォーマルで敬意を示す表現です。
手紙で使われる「敬具」や「謹白」などと同じ立ち位置で、「きちんと文章を締める」という意味があります。
一方で「よろしくお願いいたします」や「以上」などは、より日常的で柔らかい結び言葉です。
状況によって「拝」を選ぶのか、ほかの表現にするのか、相手との関係性や業界慣習によって判断しましょう。
どちらが良い悪いではなく、場面ごとの使い分けが大切です。
⑤間違った使い方とリスク
「拝」を間違った場面や書き方で使うと、逆に失礼になったり、違和感を持たれてしまうことがあります。
代表的なのは「田中 拝 先生」といった敬称との併用です。
これは日本語のマナー上、間違いとされています。
また、社内やカジュアルなグループメールで使いすぎると、「堅苦しい」「距離がある」と思われてしまう可能性もあります。
迷った場合は無理に使わず、相手やシーンに合わせて他の結び表現も検討することが大切です。
「拝」を使ったメール例文と応用パターン
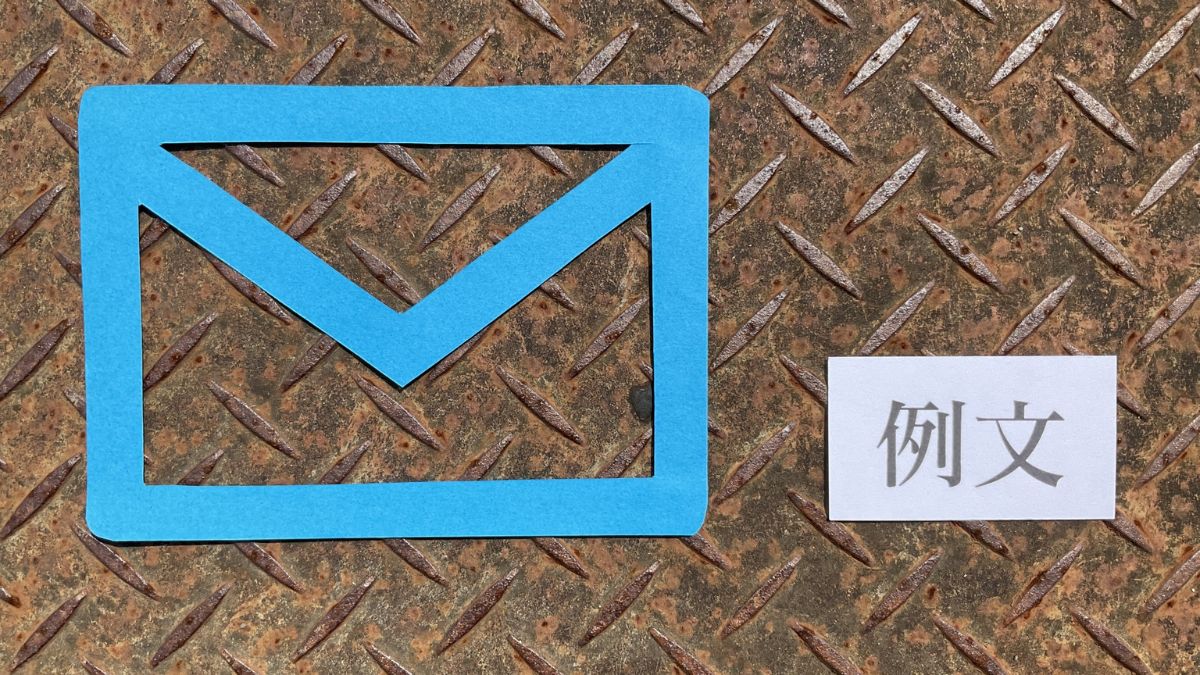
「拝」を使ったメール例文と応用パターンについて紹介します。
パターンごとに詳しい例文を見ていきましょう。
正式なビジネスメール例
正式なビジネスメールでは、特に初回のやり取りや、重要な依頼をする場面で「拝」を使うことがあります。
例:
――――――――――
株式会社〇〇〇〇
営業部 田中 拝
――――――――――
いつも大変お世話になっております。
このたびはご多忙のところ、ご対応いただき誠にありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
――――――――――
このように、署名の最後に「拝」をつけることで、相手への敬意をしっかり示します。
「拝」は本文の最後ではなく、名前の直後につけるのが自然です。
業界によっては今もよく使われています。
社内メールでの使い方
社内メールの場合、上司や目上の方へのメールで「拝」を使うことがあります。
特に、改まった依頼や報告メール、社内公募や表彰関連など、公式な場面で用いられます。
例:
――――――――――
開発部 山田 拝
――――――――――
先日はご指導いただきありがとうございました。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
――――――――――
社内でも使いすぎは禁物ですが、丁寧さを伝えたい時には効果的です。
普段の連絡やフランクなやりとりではあまり使いません。
就職活動・公的機関宛のメール例
就職活動や公的機関へのメールでは、より丁寧な表現を使うことが求められます。
そのため、署名部分に「拝」を入れることで、自分の敬意や礼儀正しさを示すことができます。
例:
――――――――――
〇〇大学 経済学部
佐藤 拝
――――――――――
お忙しい中、ご対応いただきまして誠にありがとうございます。
何卒よろしくお願いいたします。
――――――――――
公的なシーンほど「拝」の効果が発揮されやすいです。
堅苦しい印象を与えたくない場合は「拝」以外の表現も選択肢に入れましょう。
ややカジュアルな使い方
「拝」はカジュアルなメールではほとんど使われませんが、同じ部署の先輩や少し距離のある相手にあえて丁寧にしたい時には使うこともあります。
例:
――――――――――
マーケティング課
高橋 拝
――――――――――
ご多用のところご返信いただき、誠にありがとうございました。
引き続きよろしくお願いいたします。
――――――――――
このような使い方は、相手との距離感を大切にしたい時や、礼儀正しさを伝えたい時に有効です。
普段使いには向きませんが、相手やシーンを見極めて使うことで印象が良くなる場合があります。
メールの締めくくり「拝」以外の表現7つ

メールの締めくくり「拝」以外の表現7つを紹介します。
シーンや相手に合わせて適切な締めくくりを選びましょう。
①敬具
「敬具」は、日本語の手紙の結び言葉として最も有名で、ビジネス文書やフォーマルな場面で幅広く使われています。
文末の右下や署名の上などに記載し、「これで文を締めます」という意味を持ちます。
特に、手紙やメールの最初に「拝啓」などの頭語を使ったときには、結語として「敬具」で結ぶのがルールです。
メールでも改まった依頼や正式な案内などには「敬具」を使うとしっかりした印象を与えます。
少し堅い印象なので、頻繁には使いませんが、重要なメールにはおすすめです。
②以上
「以上」は、ビジネスシーンでよく使われる締めくくりの一つです。
メール本文の内容がすべて終わったことを明確に伝えることができ、簡潔でわかりやすい印象を与えます。
社内メールや簡単な報告、連絡メールなどでよく用いられています。
あまりにもフランクな場面では省略した方が良い場合もあります。
相手や内容によっては、もう少し丁寧な表現と組み合わせるとバランスが取れます。
③よろしくお願いいたします
「よろしくお願いいたします」は、あらゆるビジネスメールや日常的なメールで使える万能な表現です。
新しい依頼やお礼、締めの一言など、多様な場面にマッチします。
丁寧さを出す場合は「何卒」をつけて「何卒よろしくお願いいたします」とするのも一般的です。
改まった場面からカジュアルなやり取りまで幅広く活用できる締めのフレーズです。
迷ったときにはこの表現を使うと間違いありません。
④何卒よろしくお願い申し上げます
「何卒よろしくお願い申し上げます」は、特に丁寧さや謙譲の意を強く表現したいときに使う締めくくりの言葉です。
大切な取引先や公式な依頼、改まったやりとりの際に適しています。
普段のやり取りではやや堅いですが、失礼のないようにしたいときや、改めて感謝やお願いの気持ちを表す場合には最適です。
使いすぎには注意が必要ですが、しっかりとした印象を与えたい時にはおすすめの一言です。
目上の相手や公的な場面で選ばれる表現です。
⑤ご自愛ください
「ご自愛ください」は、相手の健康を気遣う意味が込められた締めくくりです。
季節の変わり目や、長期間のやりとりの最後などでよく使われます。
フォーマルな手紙や公式メール、年配の方へのやりとりで特に好まれます。
親しみを込めつつ、やさしい印象を与えることができます。
ビジネスメールでも使えますが、あまり堅苦しくなりすぎないよう注意しましょう。
⑥今後ともよろしくお願いします
「今後ともよろしくお願いします」は、継続的なお付き合いをお願いする際の締めの表現です。
取引先やお世話になった相手へのメールの最後によく使われます。
シンプルですが、今後の関係を大切にしたい気持ちを伝えることができます。
初回のやり取り以降や、今後も続くプロジェクト・連絡の中でおすすめの言い回しです。
社外・社内問わず、幅広いシーンで使えます。
⑦草々
「草々」は手紙の結び言葉の一つで、やや古風な印象を持っています。
主に「前略」など頭語とセットで使われることが多いですが、手短に失礼しますという意味も含まれています。
非常に丁寧で控えめな印象を与えるので、目上の方や公式な場面で使うことができます。
あまり日常的なメールでは見かけませんが、知識として知っておくと役立ちます。
手紙文化が強い業界や、フォーマルなやりとりに向いている表現です。
「拝」に関するよくある疑問・トラブル

「拝」に関するよくある疑問やトラブルをまとめて解説します。
よくある悩みを一つずつ見ていきましょう。
返信時は「拝」をどう返す?
相手がメールの署名で「拝」を使っていた場合、必ずしも自分も「拝」を使う必要はありません。
相手が目上の場合や、フォーマルなやりとりが続いている時には合わせて使うと違和感がありません。
ただし、社内やフランクなやり取りの場合は「よろしくお願いいたします」など、もう少し柔らかい表現に変えてもマナー違反にはなりません。
大切なのは「相手の立場」「メールの雰囲気」に合わせることです。
返信ごとに少しずつトーンを和らげていくのもよくあるパターンです。
社外・社内での使い分け
社外向けのフォーマルなメールや、格式が求められるやりとりでは「拝」を使うことで丁寧な印象を与えることができます。
一方で、社内や近しい間柄、カジュアルなやりとりでは、やや堅苦しくなりすぎる場合が多いです。
上司や役員など、社内でも目上の人へのメールには使う価値がありますが、普段使いにはあまり向いていません。
相手や場面に合わせて柔軟に使い分けることが重要です。
その場の雰囲気や会社の慣習も参考にしてください。
失礼にあたる場合は?
「拝」を使って失礼にあたる場面は主に「敬称とセットにする」「相手に対して直接的に使う」といった誤用の時です。
たとえば「山田 拝 先生」や「部長 拝」などは、日本語の敬語マナーとして間違いです。
必ず「自分の名前+拝」の順で、敬称はつけません。
また、あまりに堅苦しい印象を与えたり、親しみのある相手に使うと距離を感じさせる場合があります。
迷った時は他の表現を使う、あるいは会社のルールや相手の雰囲気を参考にすると安心です。
古い表現・現代の感覚
「拝」は手紙文化の名残が色濃く残る表現であり、現代ではやや古風な印象を持つ人も増えています。
若い世代やIT業界などではほとんど使われなくなっていますが、大学や官公庁、伝統産業、年配の方とのやりとりでは今も現役です。
現代のビジネスメールでは、必要に応じて使い分ける柔軟さが求められています。
自分の業界や相手の年代、会社の文化をよく見極めて選びましょう。
大切なのは「思いやり」と「相手への敬意」をしっかり伝えることです。
まとめ|メールの最後に「拝」を使う意味と正しい使い方
| 主なポイント |
|---|
| 「拝」の本来の意味 |
| メール結びで「拝」を使う理由 |
| どんな業界・シーンで使われる? |
| 使い方の注意点 |
メールの最後に「拝」と書くことで、相手への敬意や謙虚な気持ちを伝える日本独自の文化が今も息づいています。
特にビジネスや公的な場面、格式を重んじる業界では、適切に使うことで信頼感や丁寧さをアピールできます。
一方、使い方を間違えると堅苦しい印象や、逆に失礼になることもあるため、正しいマナーを知っておくことが大切です。
「拝」だけでなく、さまざまな締めくくり表現を場面や相手に応じて使い分けることで、よりスマートなコミュニケーションが実現します。
詳しく知りたい方は、文化庁「敬語の指針」
文化庁「敬語の指針」PDF
や、
厚生労働省:公的文書のマナー
なども参考にしてみてください。