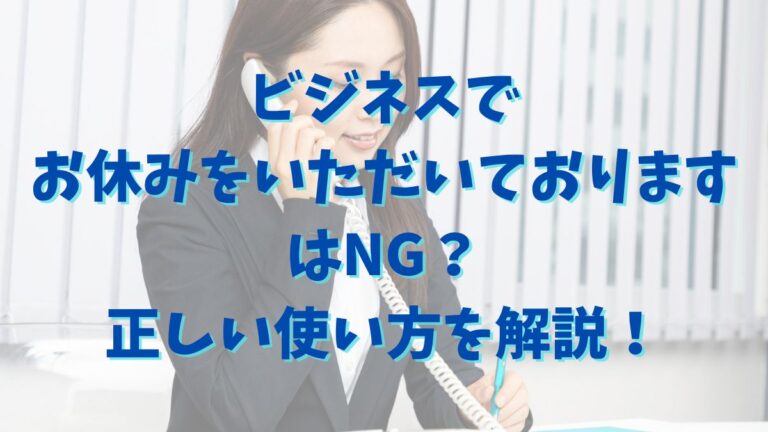この記事では社外で「お休みをいただいております」を使うのがなぜNGなのか、その理由やリスク、正しい表現やマナーについて解説します。
ビジネスの現場で、取引先やお客様に不快な印象を与えず、信頼される対応ができるポイントをまとめました。
具体的なメールや電話での案内例、社内と社外の使い分けまで、すぐに実践できる知識が満載です。
社外対応で迷ったときの不安や疑問をスッキリ解消できる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
ビジネスで「お休みをいただいております」を社外で使うのはNGの理由と注意点

ビジネスで「お休みをいただいております」を社外で使うのはNGの理由と注意点について解説します。
それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
社外メールや電話での一般的な休暇表現
ビジネスシーンで社外に対して休暇を伝える際には、できるだけ直接的かつ分かりやすい表現が好まれます。
たとえば、「お休みをいただいております」というフレーズは、社内向けには丁寧ですが、社外向けにはやや曖昧に受け取られがちです。
取引先やお客様に対しては、「〇月〇日まで不在にしております」や「現在席を外しております」といった、より事実に即した伝え方が一般的です。
また、電話の場合は「〇〇は本日不在にしております」「〇〇は只今外出中です」など、簡潔で相手に情報が伝わりやすい言い回しが適切です。
こうした表現を使うことで、相手が状況を正しく理解しやすくなり、余計な誤解や不信感を防ぐことができます。
「お休みをいただいております」がNGとされる理由
「お休みをいただいております」という言い回しが社外でNGとされる理由は、曖昧さと主観的なニュアンスにあります。
ビジネスでは、相手に具体的な状況や対応できない理由を明確に伝えることが求められます。
「お休みをいただいております」では、いつまで不在なのか、誰が代わりに対応できるのかが伝わりにくくなります。
また、「いただいております」という表現が、やや内輪的なニュアンスや、会社内部の都合に聞こえるため、取引先や顧客に配慮が足りない印象を与えることもあります。
さらに、外部の人から見ると「忙しい」「都合が悪い」という意味にも受け取られやすく、場合によっては責任回避や対応の遅れと誤解される可能性もあります。
社外でのリスクやトラブル事例
社外に対して「お休みをいただいております」と伝えたことで、実際にトラブルが発生するケースもあります。
たとえば、納期や契約に関わる重要な連絡で、「お休みをいただいております」とだけ伝えた場合、相手が急ぎの用件だった際に対応が遅れてしまうリスクがあります。
また、「自分は関係ない」という印象を与えてしまい、取引先との信頼関係に傷がつくことも考えられます。
実際に、「お休みをいただいております」と自動返信メールに記載しただけで、対応者や緊急連絡先が記載されていなかったため、重要な案件がストップしてしまったという例も報告されています。
社外に対しては、状況を明確に伝え、必要があれば代替連絡先や担当者を明記することが大切です。
休暇を伝えるときのマナーと配慮
ビジネスで休暇を伝える際のマナーは、相手の立場に立って配慮を示すことがポイントです。
単に「お休みです」「不在です」と伝えるのではなく、復帰予定日や代わりの担当者の連絡先を明記することで、相手に安心感を与えることができます。
また、メールや自動返信では「ご不便をおかけし申し訳ございません」「何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」といったお詫びやお願いの言葉を添えると丁寧です。
電話対応でも、なるべく迅速に代替対応ができる体制を整えておくと、取引先からの信頼度がアップします。
休暇の際は、自分の業務だけでなく相手のスケジュールや心配事にも配慮した案内を心がけましょう。
社外向けメール・電話で使える適切な休暇表現

社外向けメール・電話で使える適切な休暇表現について詳しく紹介します。
それぞれのポイントについて分かりやすく解説します。
メールでの丁寧な休暇案内例
社外に向けて休暇を案内する場合、メールの文面は簡潔で明確、かつ相手の立場を配慮した内容にすることが重要です。
「お休みをいただいております」という表現ではなく、「〇月〇日から〇月〇日まで不在にしております」や「本日より休暇を頂戴しております」と記載し、不在期間が明確にわかるようにしましょう。
さらに「ご不便をおかけし誠に申し訳ございません」とお詫びを添え、「休暇明け以降に順次対応いたします」など対応方針も記載すると丁寧です。
また、担当者が不在の場合は代理対応の連絡先や、復帰予定日など具体的な情報も記載してください。
例文としては以下のような形が適切です。
| 不在案内メール例文 |
|---|
| いつもお世話になっております。
誠に勝手ながら、〇月〇日から〇月〇日まで休暇を頂戴しております。 期間中はメールの確認ができません。 ご用件が急ぎの場合は、〇〇(担当者名・連絡先)までご連絡いただきますようお願い申し上げます。 ご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。 |
電話での休暇案内フレーズ
電話対応で休暇を伝える際は、短く明確に伝えることが大切です。
「〇〇は只今休暇を頂戴しておりまして、本日終日不在にしております」「〇〇は〇月〇日まで休暇をいただいております」など、現在の状況を具体的に伝えましょう。
また、相手の要件が急ぎの場合もあるため、「代わりに〇〇が対応いたしますので、担当者をお呼びしましょうか」など、すぐに対応できる姿勢を見せることが信頼につながります。
電話の取り次ぎで迷った場合は、「不在期間」「代理担当者」「折り返しの有無」をきちんと確認して案内してください。
電話での案内例をいくつかご紹介します。
| 電話対応フレーズ例 |
|---|
| 「〇〇は本日休暇を頂戴しており、不在にしております」
「〇〇は〇月〇日まで休暇をいただいております」 「ご用件を承り、休暇明けに折り返しご連絡させていただきます」 「急ぎの場合は、〇〇(代理担当者)が対応いたしますので、おつなぎしましょうか」 |
自動返信メールの注意点
休暇中の自動返信メールは、社外の相手に正確な情報を伝える役割を持っています。
「お休みをいただいております」だけでは相手が困惑することがあるため、「休暇期間」「復帰予定日」「対応できない旨」など、必要な情報を必ず記載しましょう。
また、緊急の場合の対応方法や代理の担当者を明記することで、相手の不安を和らげることができます。
自動返信の例としては、「〇月〇日まで休暇をいただいております。ご用件が急ぎの場合は、〇〇(代理担当者・連絡先)までご連絡ください」といった内容が適切です。
あらかじめ自動返信の文面は確認し、誤字脱字や不十分な情報がないかチェックしておくことが重要です。
対応者や緊急連絡先の伝え方
休暇期間中も社外からの急ぎの要件が発生することは珍しくありません。
そのため、必ず代理対応者や緊急連絡先を明記しておきましょう。
メールや自動返信には「急ぎの場合は〇〇が対応いたします」「下記の連絡先までご連絡をお願いいたします」といった記載が必要です。
連絡先の記載ミスや担当者の伝え漏れがあると、信頼関係を損なうことにつながるため注意が必要です。
チーム全体で不在時の対応フローを共有し、誰がどの連絡先を案内するか事前に確認しておくことで、スムーズな対応が可能になります。
「お休みをいただいております」は社内ならOKな理由

「お休みをいただいております」は社内ならOKな理由について詳しく説明します。
社内で「お休みをいただいております」という表現が受け入れられている理由や使い方を解説していきます。
社内で使える状況や背景
「お休みをいただいております」というフレーズは、社内の上司や同僚に対して使う分には丁寧で自然な表現とされています。
同じ会社の社員同士であれば、組織文化や休暇のルールが共有されているため、具体的な理由を細かく説明する必要がない場面も多いです。
たとえば総務や人事担当が休暇中の社員を取り次ぐ際にも、「〇〇はお休みをいただいております」と伝えても、社内の人はその状況を理解しやすいです。
また、「いただいております」という謙譲語を使うことで、相手や会社への配慮や感謝を表現することにもつながります。
社内での連携や伝達の中で、特別にかしこまりすぎず、柔らかく不在を伝えられるのがこの表現の特徴です。
社内向けと社外向けの敬語の違い
ビジネス敬語は、相手が社内か社外かによって使い方やニュアンスが変わります。
社内の場合は同じ会社の仲間として、ある程度リラックスした言葉づかいが許容されるため、「お休みをいただいております」のような社内文化に合った表現が一般的です。
一方で、社外の取引先や顧客に対しては、より客観的かつ具体的な表現が求められます。
例えば「不在にしております」「本日休暇を頂戴しております」など、誰が聞いても分かりやすいフレーズが必要です。
この違いを意識することで、社内外のコミュニケーションを円滑に進めることができます。
社内メール・口頭での使い方
社内でのメールや口頭連絡で「お休みをいただいております」を使う場合、気を付けるべきポイントもあります。
たとえば、急ぎの案件や部署をまたぐ連絡では、「何日まで休暇をいただいております」や「〇〇の理由でお休みをいただいております」と期間や理由を具体的に伝えると、相手の理解が深まります。
また、同じチームや部署内であれば、口頭で「本日お休みをいただいておりますので、よろしくお願いします」と伝えることで十分です。
業務連絡用チャットや社内メールでは、「〇〇はお休みをいただいております。ご用件は復帰後にご連絡いたします」といった簡単なフレーズが多く使われています。
社内での連絡は、形式にとらわれすぎず、状況に応じて柔軟に対応することが大切です。
誤解を防ぐための工夫
社内で「お休みをいただいております」を使う場合でも、状況によっては誤解を招くことがあります。
たとえば、同じタイミングで複数人が休む場合や、重要な案件の進行中の場合は、誰がどの期間不在かをしっかり共有しておくことが必要です。
休暇の予定は、事前にグループウェアや社内カレンダーで共有したり、メールで「〇月〇日から〇日まで休暇をいただきます」と伝えるのがベストです。
また、急な休みの場合は、チーム内で緊急対応フローを決めておくと安心です。
こうした工夫によって、社内の業務が滞らず、円滑に進むようになります。
まとめ|ビジネスで「お休みをいただいております」は社外NGの理由と使い分け
| 章内リンク |
|---|
| 社外メールや電話での一般的な休暇表現 |
| 「お休みをいただいております」がNGとされる理由 |
| 社外でのリスクやトラブル事例 |
| 休暇を伝えるときのマナーと配慮 |
ビジネスシーンで「お休みをいただいております」は、社外に対して使うと誤解や信頼低下のリスクがあるため注意が必要です。
社外では、「不在にしております」や「休暇を頂戴しております」といった分かりやすい表現で、期間や代理連絡先も必ず案内することが大切です。
社内であれば社風に合った柔らかい敬語表現として受け入れられますが、状況や相手によって言葉を選び、業務が滞らないよう情報共有やマナーに気を配りましょう。
休暇連絡で迷った際は、相手の立場やビジネスマナーを意識し、安心感と信頼を生む表現を心がけてください。
さらに詳しい情報は、下記の信頼できるサイトや公的情報も参考にしてみてください。
厚生労働省|年次有給休暇に関するQ&A
All About|ビジネスマナー 休暇中のメール・電話対応
経営者会報|休暇案内メールの正しい書き方