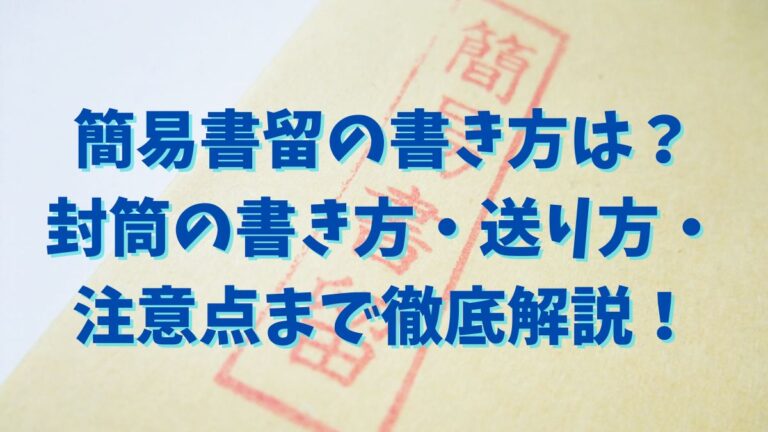「簡易書留って、どうやって書けばいいの?」「普通の封筒で大丈夫?」
そんな疑問をお持ちのあなたに向けて、この記事では封筒の正しい書き方から送り方の手順、よくある失敗例までわかりやすく解説します。
郵便局で「これで合ってる?」と不安にならないために、知っておきたい情報をギュッとまとめました。
実際の利用シーンや封筒・切手の選び方も紹介しているので、この記事を読めば簡易書留の郵送がグッとラクになりますよ。
大事な書類を確実に届けるために、ぜひ最後までチェックしてくださいね。
簡易書留の書き方を封筒で徹底解説
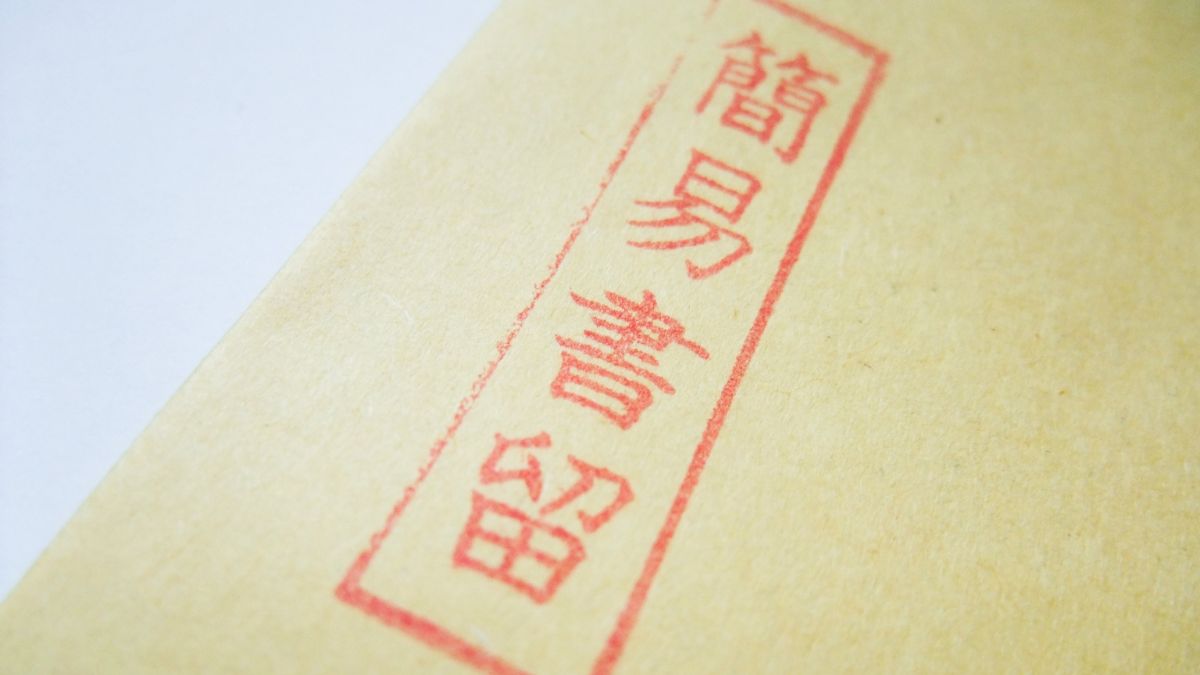
簡易書留の書き方を封筒で徹底解説します。
それでは、詳しく解説していきますね!
封筒の表面の書き方
封筒の表面は、宛名や郵便番号、住所を書く重要なスペースです。
まず、右上の郵便番号欄に宛先の郵便番号を記入しましょう。
その下に宛先の住所を「都道府県から正確に」書いていきます。
文字は大きく、はっきりと見えるように心がけてください。特に縦書きの場合、右から左へバランス良く配置すると見栄えも良くなります。
番地やビル名、部屋番号などは間違いがないように丁寧に記入してくださいね。
企業や団体宛てなら、会社名や部署名も忘れずに書きます。
「御中」や「様」の使い分けも意識すると、相手に対する礼儀も伝わりますよ〜!
封筒の裏面の書き方
裏面には、差出人の情報を書きます。
封筒の左下あたりに、差出人の郵便番号・住所・氏名を縦書きか横書きで記入しましょう。
封をする部分には、「〆」マークを書き入れて封かん済みであることを明示します。
差出人情報はトラブル時の返送にも必要なので、必ず記入してください。
特にビジネス文書や公的書類の場合、差出人が曖昧だと信頼性を損なうこともあるんですよね。
筆ペンやボールペンなど、にじみにくい筆記具で書くのがおすすめです。
差出人と宛名の正しい配置
差出人と宛名の配置は、郵便物の仕分けや配達に関わる重要なポイントです。
宛名(受取人)は封筒の中央やや右側に大きく配置します。
差出人は封筒裏面の左下に配置するのが一般的です。
両者の情報が混在しないように注意してください。
とくに白い封筒だと文字が多くなりすぎて見づらくなるので、バランスを意識して配置しましょう。
見やすく書くことで、配達ミスを防げますし、相手にも丁寧な印象を与えられますよ。
「簡易書留」と明記する位置
「簡易書留」という表記は必ず封筒表面の左下あたりに書いてください。
赤ペンで「簡易書留」と明記するのが基本です。
もし「速達」と併用する場合は、その下に「速達」と赤で書き添えましょう。
この表記がないと、通常郵便として処理される可能性もあります。
郵便局で簡易書留として差し出す際にも、職員が確認しやすくなるのでスムーズです。
ただし、書く位置が封筒のデザインや記載情報に重ならないように注意してくださいね。
「簡易書留」としっかり書かれているだけで、封筒全体の信頼感がグッと増しますよ~!
簡易書留を送る手順5ステップ
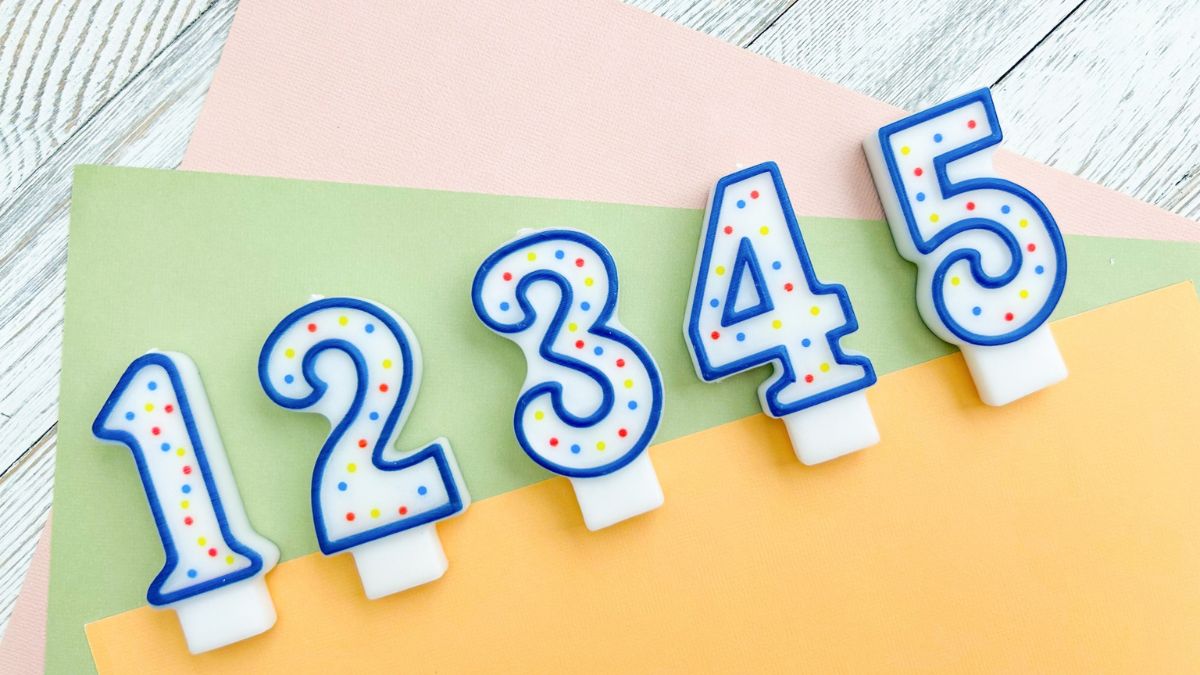
簡易書留を送る手順5ステップについて解説します。
ひとつずつ見ていきましょう!
①封筒に書類を正しく入れる
まずは、封筒に入れる書類をしっかりチェックしましょう。
重要な書類(契約書や申請書など)は、折り方にも注意が必要です。
例えば、企業宛ての書類なら「三つ折り」よりも「二つ折り」のほうが丁寧な印象を与えます。
封筒は、A4サイズなら角形2号、定型なら長形3号が一般的ですよ。
書類が中で動かないように、クリアファイルに入れてから封入するのもおすすめです。
見た目もよくなり、折れや汚れから守れるので安心ですよ〜!
②封をして差出人名を書く
次に、封筒の封をきっちりと閉じます。
のりやテープでしっかり封をしたら、封かん部分に「〆」や「封」といった印を忘れずに。
そのあと、裏面の左下に自分(差出人)の郵便番号・住所・氏名を記入します。
郵便局側は返送が必要な際、この差出人情報を元に戻すので、正確に書いてください。
ちなみにボールペンや油性ペンで書くとにじみにくく、長期間残りやすいですよ。
書き忘れがあると、受付時に時間がかかることもあるので、ここで一度見直してくださいね!
③郵便局で差出票を記入
簡易書留は、窓口で「書留・特定記録郵便物等差出票」を書く必要があります。
この差出票には、宛先・差出人・内容物・簡易書留の種類などを記入します。
差出票は郵便局に用意されているので、事前に持っていなくても大丈夫です。
記入台で落ち着いて書く時間を取るため、少し時間に余裕をもって行くと安心ですよ。
もし不明点があれば、窓口のスタッフさんに相談すると丁寧に教えてくれます。
「こう書いたらOK!」という正解パターンも見せてくれるので、初心者でも安心です♪
④料金を支払い、控えを受け取る
差出票の記入が終わったら、封筒と一緒に窓口へ提出します。
簡易書留は、通常の送料+簡易書留料金(2025年6月現在で320円)が加算されます。
重さによって送料は変わりますので、窓口で測ってもらってください。
例として、長形3号封筒で25g以下の文書を送る場合は、84円+320円=404円が目安です。
支払いが終わると、受付控え(レシートのような用紙)を受け取れます。
この控えに「追跡番号」が記載されているので、大切に保管してくださいね!
⑤追跡番号で配達状況を確認
最後に、受け取った控えに記載された「お問い合わせ番号(追跡番号)」を使って、郵便の配達状況を確認できます。
日本郵便の公式サイトや、郵便局アプリに追跡番号を入力するだけで、配達状況がすぐにわかります。
「引受」「配達中」「配達完了」などのステータスが表示されるので、安心ですね。
特にビジネス文書や大切な申請書など、確実に届いたか知りたいときに重宝します。
配達完了までチェックできるのが、簡易書留の大きな魅力でもあります!
しっかり確認して、相手にも安心してもらいましょう〜。
簡易書留に適した封筒と切手の選び方

簡易書留に適した封筒と切手の選び方について詳しく解説します。
それでは順にチェックしていきましょう!
定型・定形外どちらでもOK
簡易書留に使う封筒は、定型でも定形外でも問題ありません。
たとえばA4サイズの書類をそのまま送りたい場合は「角形2号」の定形外封筒がピッタリ。
一方、小さめの書類やメッセージカードなどであれば「長形3号」の定型封筒がちょうどいいサイズです。
ただし、厚さ1cmを超えると定形外になり、料金も上がります。
送る内容に合わせて、封筒のサイズと形状を選ぶようにしましょう。
ちなみに、重さとサイズの基準は郵便局の窓口でも確認できますよ〜!
白無地や茶封筒どちらが良い?
封筒の色にルールはありませんが、相手の印象を考えると白無地がベターです。
ビジネスや公的書類を送る場合、白の封筒は清潔感とフォーマルさを与えるからです。
一方、茶封筒はコスト的には安価で便利ですが、用途によってはラフな印象になりがちです。
「どちらを使うべき?」と迷ったときは、相手や送る書類の重要度で判断してくださいね。
フォーマルな書類なら白、個人宛てやカジュアルな内容なら茶でも問題なしです!
重さ別の料金と切手の貼り方
簡易書留は「通常の郵便料金」+「簡易書留料金(320円)」で構成されています。
以下の表は、一般的な重さと料金の例です(2025年6月時点):
| 重量 | 通常郵便料金 | 簡易書留加算 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 25g以下(定型) | 84円 | 320円 | 404円 |
| 50g以下(定型) | 94円 | 320円 | 414円 |
| 100g以下(定形外) | 140円 | 320円 | 460円 |
切手の貼り方に決まりはありませんが、封筒の右上にきれいに並べて貼りましょう。
「端が剥がれそう」「枚数が多すぎる」といった場合は、窓口で一括支払いも可能です。
料金不足になると差し戻しされるので、必ず郵便局で確認してくださいね!
返信用封筒を同封する際の注意点
相手に返信を依頼する場合、返信用封筒を同封することがあります。
このときの注意点は以下のとおりです:
- 返信用封筒にも切手を貼っておく
- 返信先(自分の住所)を明記する
- 「返信用」と記載してわかりやすくする
また、返信用封筒も含めた全体の重さで料金が変わる可能性があるので要注意です。
場合によってはクリアファイルにまとめて封入したほうが、見栄えもよくスムーズに処理されます。
ビジネスマナーとしても、返信用封筒の準備がしっかりしていると丁寧な印象を与えますよ〜!
簡易書留でよくある失敗と注意点
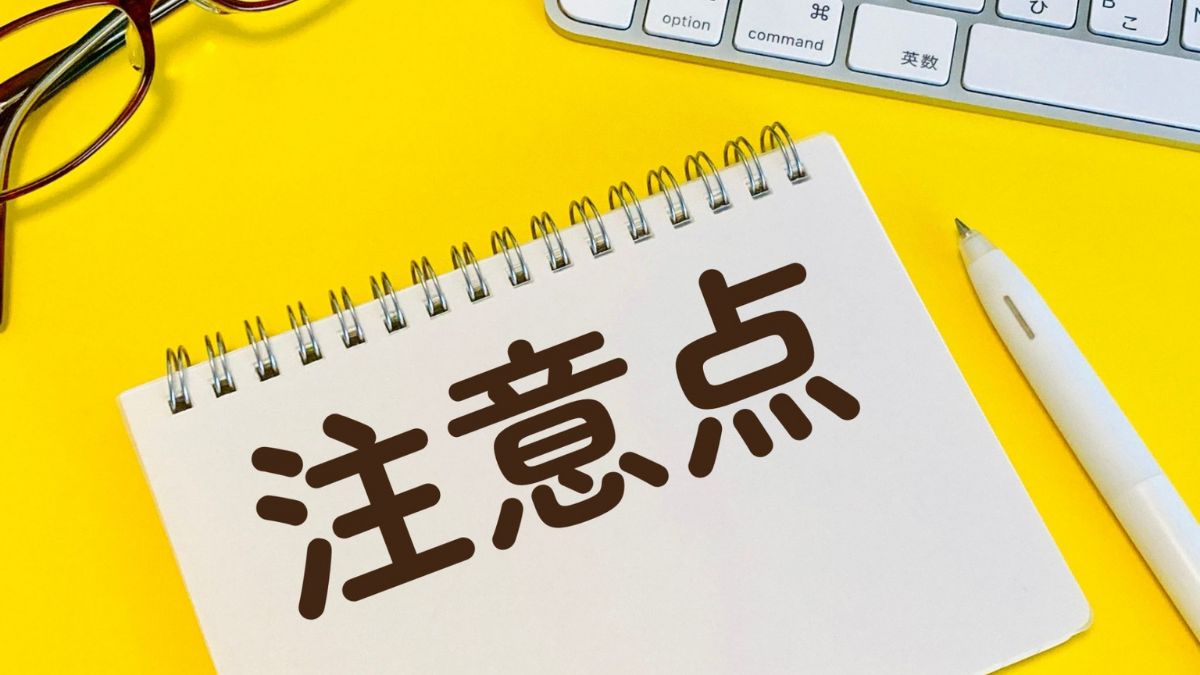
簡易書留でよくある失敗と注意点について解説していきます。
実際によくある失敗例を確認して、トラブルを未然に防ぎましょう!
「書き忘れ」「記入ミス」に注意
封筒に必要事項を書き忘れてしまうミス、実はかなり多いです。
たとえば差出人の住所を書いていない、宛先の名前に「様」や「御中」が抜けている、といったケースですね。
こういったミスは、配達トラブルや返送の原因になります。
また、書留差出票の記入欄を間違える方も少なくありません。
焦って書くと、字が汚くて読めなかったり、内容が不完全だったりします。
提出前には、必ず自分の記入を見直す「ひと呼吸」を忘れずにしましょう〜!
料金不足で返送されるケース
簡易書留では「通常料金+簡易書留料金」が必要です。
ここを間違えて、通常の切手だけを貼って出してしまうと、残念ながら返送されてしまいます。
特にポスト投函では気づきにくく、あとから戻ってきてしまうことが多いです。
「このくらいなら定形でいけるかな…?」という自己判断は禁物です!
郵便局で正確に測ってもらい、必要な切手代を教えてもらうのが確実です。
失敗すると余計な時間と手間がかかるので、ここは本当に慎重に確認してくださいね!
封筒サイズ超過による追加料金
封筒のサイズが想定より大きかったり、厚さが1cmを超えていると「定形外郵便」扱いになってしまいます。
これに気づかず定形のつもりで切手を貼ると、やっぱり返送コースまっしぐらです。
特に返信用封筒やクリアファイルを入れる場合、重さだけでなく「厚さ」にも注意が必要です。
ちょっとした差で料金が変わってしまうこともあります。
封筒に詰めたあとで、郵便局で「厚さゲージ」を通してもらうと確実ですよ!
差出時の混雑で時間がかかることも
簡易書留は窓口での手続きが必要なので、混雑時にはかなり待たされることもあります。
月末や朝イチ、お昼前後は特に混雑しやすい時間帯です。
時間に余裕がないときに行くと、イライラしたり、差出票を間違えたりしがちです。
なるべく時間帯をずらしたり、事前に差出票の記入を済ませておくのがおすすめです。
落ち着いて準備することで、失敗やストレスを防げますよ~!
一般書留・現金書留との違いとは?

一般書留・現金書留との違いについて詳しく解説していきます。
似ているようで実はけっこう違う3つのサービス。しっかり違いを押さえておきましょう!
損害賠償の範囲の違い
まず大きな違いは、万が一郵便物が事故に遭った際の「補償額(損害賠償)」です。
簡易書留は、実際の損害が5万円まで補償されます。
一方、一般書留は最大500万円まで補償され、現金書留は現金そのものの金額が補償対象となります。
補償金額が高いぶん、送る書類や物の重要度によって使い分けることが大事です。
大切な証明書類や貴重品を送るときは、補償内容をよく確認してくださいね。
追跡記録の内容の違い
簡易書留では「引受」と「配達」の2つのステータスが追跡記録として残ります。
つまり、送ったときと届いたときの記録が確認できるわけですね。
しかし、一般書留・現金書留では、さらに「中継地点」や「不在持ち戻り」などの細かい経過も記録されます。
そのため、より細かな追跡が必要な場合は、一般書留や現金書留を選んだ方が安心です。
誰がいつ受け取ったかまで確認したい書類なら、一般書留が最適ですよ。
送るべき書類の種類で使い分け
簡易書留は、主に「重要だけど高額ではない」文書に向いています。
たとえば、契約書、申請書類、証明書のコピーなどですね。
一方、現金そのものを送る場合は必ず「現金書留」にしなければなりません。これは法律上のルールです。
また、原本証明や遺言書のように超重要な文書は、補償額が高い一般書留が望ましいです。
送るものの「金銭的・法的価値」を基準にして選ぶとわかりやすいですよ!
料金の違いを比較して選ぶ
料金にももちろん違いがあります。
| 種類 | 追加料金(2025年現在) | 主な用途 | 補償額上限 |
|---|---|---|---|
| 簡易書留 | 320円 | 申請書・証明書のコピーなど | 5万円まで |
| 一般書留 | 430円〜(損害額に応じて増加) | 原本・高価な文書など | 500万円まで |
| 現金書留 | 430円+損害要加算額 | 現金を郵送する場合 | 実額まで |
予算を抑えつつ、安全に届けたいなら簡易書留。
確実性と補償を重視するなら、少し費用が上がっても一般書留や現金書留を選ぶのが安心です!
簡易書留が便利なおすすめ利用シーン

簡易書留が便利なおすすめ利用シーンについて紹介していきます。
「この書類、大事だけどどうやって送るべき?」そんな時の参考にしてくださいね!
重要な書類の提出時(役所・確定申告)
市役所や区役所への提出書類、確定申告の郵送など、「届かなかったら困る!」という場面では簡易書留が非常に役立ちます。
たとえば、マイナンバー関連の申請書や住民票請求なども対象です。
追跡番号で「届いたかどうか」が確認できるので、役所側とのやり取りもスムーズになります。
確定申告では「提出期限」が厳格なので、確実に届いたという証明が取れることは超重要です。
提出後の控えや郵送履歴をきちんと保存しておくと、後からトラブル回避にもなりますよ〜!
チケットや証明書の送付
ライブや舞台のチケット、検定合格証書、資格証明書など、「再発行が難しいもの」を送るときにも簡易書留はオススメです。
とくにオークションやフリマサイトでチケットを取引する場合、追跡可能な発送方法を求められることが多いです。
簡易書留なら「発送した証拠」「配達された証拠」どちらも取れるので、お互いに安心ですね。
資格証明など、原本を相手に提出しなければならないときにもピッタリです。
封筒の保護性を上げたいときは、厚紙やクリアファイルを活用してくださいね!
契約書や申請書の郵送
企業間での契約書のやり取り、各種申請書や同意書の送付にも簡易書留はよく使われます。
郵便事故で届かなかった場合、大きな信用問題に発展することもありますよね。
簡易書留であれば配達証明もつけられるので、「確かに届いた」という記録が残せます。
特に契約書の「原本返送」などでは、簡易書留または一般書留が基本となっている企業も多いです。
信頼関係を保つためにも、安全で確実な郵送手段を選びましょう。
ビジネス書類の安全な送付方法
社外へ請求書や見積書を郵送する際、「誰が受け取ったか」まで把握したいこともありますよね。
そんなときにこそ、簡易書留が便利なんです。
内容証明までは必要ないけど、普通郵便じゃ不安…というケースで、まさに“ちょうどいい存在”。
企業の押印済み書類や、公的機関へ提出する文書などは、簡易書留で送るだけで信頼性アップにつながります。
社内の発送ルールとして簡易書留を使う会社も増えてきてますよ〜。
まとめ|簡易書留の書き方と注意点
| 簡易書留の封筒の書き方ポイント |
|---|
| 封筒の表面の書き方 |
| 封筒の裏面の書き方 |
| 差出人と宛名の正しい配置 |
| 「簡易書留」と明記する位置 |
簡易書留を使えば、大切な書類を確実に相手へ届けられます。
そのためには、封筒の書き方から郵便局での手続き、料金の確認まで、事前準備がとっても大切です。
封筒の表面と裏面を正しく記入し、「簡易書留」の文字も忘れずに。
差出票の書き方や、切手の金額もしっかり確認して、郵便事故のないように送りたいですね。
この記事を参考にしていただければ、もう簡易書留で迷うことはありませんよ。
もっと詳しい情報は、日本郵便の公式サイトもチェックしてみてくださいね。