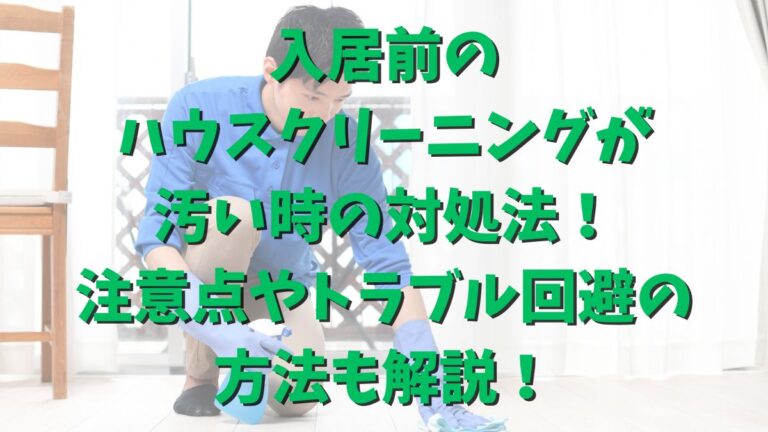入居前にハウスクリーニングが「汚い」と感じてしまった経験はありませんか。
せっかくの新生活、最初から不快な気持ちになりたくないですよね。
この記事では、「入居前 ハウスクリーニング 汚い」という悩みを解決するために、実際によくあるトラブルや対応方法、入居前にチェックすべきポイント、費用負担の仕組みまで分かりやすく解説しています。
読んでいただければ、汚れやクリーニングの不安を事前に防ぎ、安心して新しい暮らしを始められる知識が手に入ります。
気持ちよく引越ししたい方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
入居前ハウスクリーニングが汚い場合の対応方法

入居前ハウスクリーニングが汚い場合の対応方法について解説します。
それでは、それぞれのポイントを詳しく説明していきます。
原因を確認する
まず最初に、入居前のハウスクリーニングが汚いと感じた場合は、その原因をしっかり確認しましょう。
部屋全体が汚れているのか、水回りやエアコンなど特定の場所だけなのか、クリーニングが行われた形跡があるかなどを細かく見ていきます。
また、前の入居者が退去した後に十分な清掃が行われていないこともありますので、どこが気になるのかメモを取りながらチェックするのが大切です。
例えば、床のほこりや髪の毛が残っている、キッチンや浴室のカビや水垢が落とされていない、エアコンの内部がカビ臭いなど、具体的な場所と内容を整理しておくと後の交渉もスムーズになります。
この時点で原因や状況をしっかり把握することで、後々の対応がはっきりしてきます。
管理会社や大家に相談する
入居前に部屋が汚いと感じた場合は、できるだけ早く管理会社や大家に相談しましょう。
入居のタイミングによっては、すぐに対応してもらえることも多いです。
具体的には、気になった箇所や汚れをリストアップし、写真も添えて伝えると状況が伝わりやすくなります。
電話だけでなく、メールやチャットなど記録が残る方法で相談するのがベストです。
「入居したばかりで気持ちよく住み始めたい」といった素直な気持ちも伝えると、相手も柔軟に対応してくれる場合が多いですよ。
再クリーニングを依頼する
明らかにハウスクリーニングが不十分だった場合は、遠慮せずに再クリーニングを依頼しましょう。
管理会社や大家によっては、入居後でも迅速にクリーニング業者を手配してくれることもあります。
「入居前に掃除が行き届いていないので、もう一度清掃をお願いできますか」と丁寧に依頼すれば、大抵は対応してもらえます。
ただし、すべての場所が再クリーニングの対象になるわけではないので、契約内容や過去のやりとりも確認しておくと安心です。
あらかじめ再クリーニングの範囲や日程も確認し、入居後にトラブルにならないように注意してください。
証拠を写真で残す
トラブル防止のためにも、入居前や入居時に汚れている箇所は必ず写真で記録しておきましょう。
できれば日付もわかる形で複数枚撮影し、後で管理会社や大家に提出できるようにしておくと安心です。
写真があることで「この汚れは自分がつけたものではない」という証明にもなりますし、退去時のトラブル防止にも役立ちます。
また、必要に応じて動画でも記録を残しておくと、より状況が伝わりやすくなります。
証拠を残すことは、後からクリーニング代を請求されることを防ぐ意味でも非常に大事なポイントです。
入居前に部屋が汚れている理由

入居前に部屋が汚れている理由について解説します。
それぞれの理由について、詳しく説明していきます。
クリーニングのタイミングの違い
入居前に部屋が汚れている理由のひとつが、クリーニングのタイミングの違いです。
賃貸物件では、前の入居者が退去してからすぐにハウスクリーニングを行うケースと、新しい入居者が決まってからクリーニングを実施するケースがあります。
前者の場合、クリーニングから実際の入居までに時間が空いてしまうと、ほこりやゴミがたまってしまうことがよくあります。
一方、入居者が決まってからクリーニングする場合でも、短期間で作業が終わらないことや、スケジュールの関係で急ぎ作業になりやすい傾向があります。
クリーニングのタイミング次第で、入居前に部屋が汚れていると感じることがあるのです。
クリーニングの質のばらつき
ハウスクリーニングの質にも大きな差があります。
依頼されるクリーニング業者によって、掃除の丁寧さや作業範囲、使う洗剤の種類などが異なります。
予算やスケジュールに余裕がない場合は、最低限の掃除だけで終わってしまうこともあります。
また、安価なプランだと目立つところだけを簡単に掃除し、細かい部分まで手が回らないことも多いです。
こうした質のばらつきが、入居前に「部屋が汚い」と感じる大きな原因になります。
エアコンや水回りはオプションの場合もある
エアコンや水回りのクリーニングがオプションになっている場合も多いです。
多くの物件では、ハウスクリーニングの基本範囲にエアコン内部や換気扇、浴槽の裏側などが含まれていません。
入居者が追加料金を払って依頼しない限り、表面だけの簡易清掃で済ませるケースが少なくありません。
特にエアコンの内部クリーニングは、別途オプション扱いとなることが多く、カビやほこりが残ったままになっていることも。
水回りも同様で、キッチンやトイレの細かい汚れが残っていることがあります。
大家や前入居者が自分で清掃している
物件によっては、専門のクリーニング業者ではなく、大家や前の入居者が自分で掃除している場合もあります。
個人オーナーの物件や築年数が古い物件ほど、その傾向が強いです。
プロと違い、掃除のレベルにどうしても差が出てしまい、汚れが残ってしまうことが多いです。
また、忙しさや知識不足から十分な清掃がされていないことも珍しくありません。
大家や前入居者が清掃を担当した場合は、引き渡し前に必ず現地で状態を確認することが大切です。
入居前に確認すべきチェックポイント

入居前に確認すべきチェックポイントについて詳しく説明します。
それぞれのポイントを具体的に解説していきます。
内見時の汚れチェックリスト
内見の時は、部屋の隅々まで自分の目でチェックすることが大切です。
床やフローリング、畳の汚れや傷、エアコンのフィルターや吹き出し口、キッチンや浴室、トイレなどの水回りもよく確認しましょう。
排水口の臭いや詰まり、壁紙のシミやカビ、窓やサッシの汚れ、備え付けの家電の動作状況など、できるだけ細かくチェックするのがおすすめです。
気になる箇所はスマホで写真を撮ったり、メモを残しておくと後でトラブルを防ぎやすくなります。
実際にドアや窓を開けてみる、スイッチや換気扇を動かしてみるなど、生活するイメージで確認すると見落としが減ります。
契約前にクリーニングの範囲を確認する
契約前に、どこまでクリーニングされるのか、その範囲をはっきりさせておきましょう。
特にエアコン内部や換気扇、浴槽の裏側などは、オプション扱いになっている場合が多いです。
賃貸契約書や重要事項説明書に「ハウスクリーニング実施」と書かれていても、実際には「表面のみの簡易清掃」しかしていないこともあります。
不明点があれば管理会社や仲介会社に遠慮せず確認し、納得した上で契約することが大切です。
清掃範囲の記載がなければ、どこまで実施するのか事前に書面で残してもらうと安心です。
クリーニングが入る時期を聞く
クリーニングがいつ入るのか、その時期も事前に聞いておくことが重要です。
前の入居者の退去後すぐに行う場合と、新しい入居者が決まってから実施する場合では、部屋の状態が大きく異なります。
「入居前に必ずクリーニングが入るのか」「そのスケジュールはいつか」など、具体的なタイミングを確認しておきましょう。
クリーニング後から入居までに日数が空く場合は、再度簡単な掃除をお願いできるか聞いてみるとより安心です。
こうした事前確認が、入居後のトラブル防止につながります。
気になる部分は事前に交渉する
内見時や契約前に、少しでも気になる汚れや傷、設備の不具合があれば、その場で必ず交渉しましょう。
「ここはクリーニングしてもらえますか」「この傷は修繕してもらえますか」と具体的に伝えるとスムーズです。
後から「言った・言わない」にならないよう、メールや書面など証拠が残る形で依頼すると安心です。
また、対応内容や約束した事項も念のため記録しておくと、トラブル時に強い味方になります。
気になる部分は遠慮せず、積極的に伝えて交渉しておきましょう。
ハウスクリーニング費用と負担範囲

ハウスクリーニング費用と負担範囲について詳しく解説します。
それぞれのポイントを、具体的に説明していきます。
大家・管理会社が負担する部分
賃貸物件のハウスクリーニング費用は、基本的に大家や管理会社が負担するケースが多いです。
特に前の入居者の退去後に行うクリーニングは、「原状回復」として物件の管理側が責任を持って実施します。
例えば、経年劣化による壁や床の汚れ、備え付け設備の簡単な掃除、キッチンや浴室の基本的な清掃などが該当します。
また、敷金の中にクリーニング代が含まれている場合も多く、その場合は退去時に清掃費用が差し引かれることが一般的です。
国や自治体のガイドラインでも、通常使用による汚れや老朽化は大家や管理会社の負担とされています。
入居者が負担する部分
一方で、入居者が負担するクリーニング費用も存在します。
主に、喫煙によるヤニ汚れ、ペットの臭い、故意や過失による大きな汚れや破損、長期間の掃除不足によるカビやしつこい汚れなどが該当します。
また、エアコン内部や換気扇などのオプションクリーニング、原状回復義務を超えるような特別な清掃も入居者負担になることが多いです。
契約内容によっては、入居時や退去時にクリーニング費用が別途請求されることもあるので、事前にしっかり確認しておきましょう。
特に、独自ルールを設定している管理会社や大家もいるため、念入りに確認しておくと安心です。
費用トラブルを防ぐ方法
ハウスクリーニングの費用トラブルを防ぐには、入居前からの情報収集と記録が大切です。
入居時や退去時の状態を写真で残しておくと、「この汚れは誰の責任か」を証明しやすくなります。
また、契約書や重要事項説明書をよく読み、クリーニング代や負担範囲についてしっかり把握しておきましょう。
気になる点があれば、遠慮せず管理会社や大家に質問し、不明点はそのままにしないことがポイントです。
「思ったより請求が高い」「どこまで自分が払うのか分からない」といったトラブルを未然に防げます。
契約書やガイドラインを確認する
ハウスクリーニング費用や負担範囲は、契約書や自治体のガイドラインに明記されています。
特に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や「賃貸住宅紛争防止条例」などは一度目を通しておくのがおすすめです。
契約前に説明がなかった場合でも、疑問に思ったことは必ず確認し、できれば書面で回答をもらいましょう。
ガイドラインを参考にして、納得できる形で契約を進めることで、後からのトラブルを大きく減らせます。
正しい知識と準備が、余計な費用負担を防ぐ最強の対策となります。
入居後に部屋が汚かった時のトラブル防止術

入居後に部屋が汚かった時のトラブル防止術について詳しく解説します。
それぞれのポイントを具体的に説明します。
写真で証拠を残す
入居後に部屋が汚れていた場合、まず最初に行うべきことは「証拠写真を撮る」ことです。
汚れている箇所や傷んでいる部分をスマートフォンやデジカメで撮影し、日付や状況が分かるように記録を残しておきましょう。
床や壁、キッチン、水回り、エアコン、ベランダ、収納内部など、気になる場所はすべて細かく撮影しておくと安心です。
後から「この汚れは入居者がつけたもの」と誤解されないためにも、証拠を残しておくことが大切です。
写真だけでなく、必要に応じて動画でも記録しておくと、さらに説得力が高まります。
早めに管理会社へ連絡する
証拠を残したら、できるだけ早く管理会社や大家に連絡しましょう。
「入居時からこの状態だった」と伝えることで、後の責任の所在を明確にできます。
連絡手段は電話でも良いですが、メールや公式チャットなど、やり取りが記録に残る方法を使うのがおすすめです。
連絡内容には「どの箇所が、どのように汚れているか」を具体的に書き、写真も添付すると対応がスムーズになります。
早めに連絡することで、管理会社や大家側も誠実に対応してくれるケースが多いです。
掃除のやり直しや費用負担を交渉する
汚れや傷みが明らかに前入居者や管理側の責任であれば、再度クリーニングを依頼したり、費用負担の交渉をしましょう。
「このままでは生活に支障がある」「気持ちよく新生活を始めたい」と率直に伝えて構いません。
再クリーニングや修繕をしてもらう場合、対応内容や日程をしっかり確認し、必要であれば書面で残してもらうと安心です。
もし費用負担を求められた場合は、「ガイドライン」や「契約内容」と照らし合わせて正当性を確認してください。
不明点や納得いかない場合は、無理に支払わず、まずは説明や根拠を求めましょう。
困った時は第三者機関や消費生活センターに相談
自分だけでは解決できない場合や、管理会社・大家の対応に納得できない時は、第三者機関や消費生活センターに相談しましょう。
全国の消費生活センターや、自治体の住まい相談窓口などが無料でアドバイスをくれます。
相談時には、これまでのやりとりの記録や証拠写真、契約書なども用意しておくとスムーズです。
専門家に間に入ってもらうことで、解決に向けて動きやすくなり、余計なトラブルを避けられます。
一人で抱え込まず、適切な機関を活用して安心して新生活をスタートさせましょう。
まとめ|入居前ハウスクリーニングが汚い時の対処と注意点
| ポイント |
|---|
| 原因を確認する |
| 管理会社や大家に相談する |
| 再クリーニングを依頼する |
| 証拠を写真で残す |
入居前にハウスクリーニングが汚いと感じた時は、まず原因を冷静に確認し、証拠をしっかり写真で残しましょう。
管理会社や大家に早めに相談し、再クリーニングや修繕など必要な対応を依頼することが大切です。
クリーニングの範囲や費用負担の区分も事前にチェックして、トラブルを未然に防ぎましょう。
もし対応に納得できない場合や一人で解決が難しい場合は、消費生活センターなど第三者機関へ相談することで、安心して新生活をスタートできます。
信頼できる最新ガイドラインや相談窓口の参考リンクもあわせてチェックしてみてください。