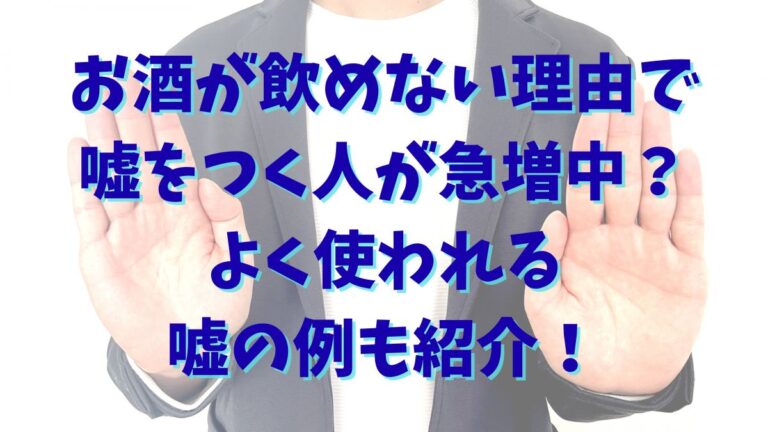「お酒が飲めない理由で嘘をついたことがある」そんな経験、ありませんか?
飲み会や職場の付き合い、友人との集まりなど、さまざまな場面で「飲めない」と伝えるのが気まずい時って意外と多いものです。
この記事では、お酒が飲めない理由で嘘をつく人がなぜ増えているのか、その本当の背景やよく使われる断り方、メリット・デメリット、そしてどんな場面でその嘘が許されるのか、詳しく解説しています。
無理に飲まなくて大丈夫な時代だからこそ、自分の気持ちを大切にできるヒントがきっと見つかります。
あなたもぜひ最後まで読んでみてくださいね。
お酒が飲めない理由で嘘をつく本当の背景

お酒が飲めない理由で嘘をつく本当の背景について詳しく解説します。
それでは、それぞれのポイントについて順番に解説します。
お酒を断るときの心理
お酒が飲めない理由で嘘をつくとき、多くの人がまず気にするのが「場の空気」や「人間関係」です。
たとえば、せっかくの飲み会で自分だけが飲まないと「ノリが悪い」と思われるんじゃないか、と心配になることがあります。
実際、周囲にどう見られるかが気になって、正直に「今日は飲みたくない」「お酒が苦手」と伝えづらいシーンは意外と多いです。
特に会社の飲み会や、あまり親しくない人との集まりでは、「飲めない」と言い出しにくい雰囲気があります。
だからこそ、あえて「飲めない」と嘘をついて場をやりすごす人が多くなっています。
こうした心理は、「断る勇気がない」というより、「できるだけ角を立てたくない」という気持ちが根本にあるのです。
体質や健康を理由にするケース
お酒を断るとき、体質や健康を理由にするのは定番のパターンです。
たとえば「体質的に弱いから」「すぐ赤くなるから」などと言えば、あまりしつこく誘われることもありません。
健康を大事にしている、という印象を与えることで、周囲も納得しやすくなります。
さらに最近では、健康志向の高まりや、アルコールハラスメント(いわゆるアルハラ)への意識も高くなっているため、体質や健康を理由にする人は増えています。
本当は飲めるけど体調や健康を理由にすることで、場の空気を壊さずに済ませられるメリットがあるわけですね。
職場や飲み会で嘘をつく背景
職場の飲み会や、会社の付き合いの場では「お酒が飲めない」と嘘をつく人も少なくありません。
理由はシンプルで、「強制的に飲まされるのがイヤ」「酔いたくない」「仕事上のトラブルを避けたい」などです。
特に、上司や目上の人からすすめられると断りにくいことも多いですが、「体質的に飲めません」と言えば角が立ちません。
本当は飲めるのに、あえて飲めないふりをして自分を守る。そんな選択をする人が多いのは、今の日本社会ならではの現象かもしれません。
また、飲み会が続くシーズンなどは「体調を気遣っている」という理由をつけることで、負担を減らす工夫をする人もいます。
人間関係を守るために嘘をつく理由
「お酒が飲めない」と嘘をつくことで、人間関係を円滑に保ちたいと考える人も多いです。
正直に断ることで、相手に「付き合いが悪い」「ノリが悪い」と思われたくない。そんな気持ちが働く場面は多いでしょう。
とくに、グループの中で孤立したくない人や、相手の機嫌を損ねたくない場合に「嘘」が選択肢になることが多いです。
また、相手が酔っていたりテンションが高い場合、本音を伝えるよりも「飲めない」と嘘をついたほうがその場が丸く収まることもあります。
人間関係のバランスをとるための“方便”として、嘘を活用している人もいるのです。
お酒が飲めない理由でよく使われる嘘の例5つ

お酒が飲めない理由でよく使われる嘘の例を5つ紹介します。
それぞれの嘘の例について、実際によく使われている背景や、そのメリット・デメリットを詳しく解説していきます。
健康上の理由を伝える
「健康診断の前だから」「体調が良くないから」「肝臓の数値が悪くて医者に止められている」など、健康上の理由を挙げてお酒を断るケースはとても多いです。
この言い訳は納得感があり、相手も「無理に飲ませてはいけない」と感じやすいため、波風が立ちにくいのが特徴です。
とくに年齢を重ねてくると健康を気遣う人が増えるので、自然な形で断りやすくなります。
本当は健康そのものでも、「最近血圧が高くて…」「検査の結果が心配で…」といった言い回しは、職場でも友人同士でもよく使われています。
ただし、何度も同じ理由を使うと不自然に思われることがあるので、注意が必要です。
車を運転する予定があると伝える
「この後車を運転しないといけないから」「家まで運転して帰るから」という理由でお酒を断るのも、非常にポピュラーです。
日本では飲酒運転が厳しく取り締まられているため、この言い訳はほぼ絶対的な拒否理由として通用します。
たとえば郊外での集まりや、帰宅の足が車になる地域ではよく使われる方法です。
「車で来ているので」と一言添えれば、相手も深追いしてこないのが大きなメリットです。
ただ、都市部など車の必要がない場所では使いにくい場合もあります。
薬を服用していると伝える
「今薬を飲んでいるから」「薬の関係でお酒はやめておく」など、薬の服用を理由にする断り方も非常に使われています。
薬とアルコールは基本的に相性が悪い、ということは多くの人が知っているので、あまり追及されずにすみます。
とくに「抗生物質を飲んでいる」「花粉症の薬を飲んでいる」など、具体的な薬名を出すと説得力がアップします。
本当に薬を飲んでいない場合は、薬の名前や病気の内容までは答えないようにすると無理なく嘘をつけます。
ただし、頻繁に使いすぎると「あれ、前も薬って言ってなかった?」と疑われることもあるので、使いどころが大切です。
翌日の予定が早いと伝える
「明日の朝早いから」「朝から大事な用事があるから」という理由でお酒を断るのは、特に社会人の間でよくあるパターンです。
仕事の大事な会議や、遠方への移動、家族との約束など、いろいろなバリエーションで応用が効きます。
たとえば「明日重要なプレゼンがあるので今日はやめておきます」と言えば、仕事に真面目な印象も与えられます。
予定を理由にすることで、その場だけでなく二次会や三次会も断りやすいというメリットもあります。
ただし、休日や連休前の飲み会ではやや使いにくいことがあります。
宗教や家庭の事情を理由にする
「宗教上の理由でお酒は飲まない」「家庭のルールでお酒は禁止されている」などの理由を挙げる方法も存在します。
宗教上の理由は、相手もあまり突っ込めない話題なので、確実に断りたい場合に使う人もいます。
また、家庭環境や親の方針などを理由にすることで、「そうなんだ」と自然に納得してもらいやすいです。
たとえば「親が厳しくて」「家族の決まりで」など、少しオーバーに伝えることでしつこい誘いも回避できます。
ただし、親しい友人や家族にはバレやすいので、使う相手や場面は選んだほうが無難です。
お酒が飲めない理由で嘘をつくメリット5つ

お酒が飲めない理由で嘘をつくメリットについて、代表的な5つを解説します。
それぞれのメリットについて、詳しく説明していきます。
気まずさを避けるため
お酒が飲めない理由で嘘をつく最大のメリットは、場の空気を壊さずに気まずい思いをせずに済むことです。
たとえば、みんなで盛り上がっている飲み会の席で「今日は飲みたくない」とだけ伝えると、その場が一瞬しらけてしまうこともあります。
そんな時、「体質的に飲めない」や「医者に止められている」といった嘘を使うことで、スムーズにお酒を断ることができます。
特に、会社やサークルなど、あまり親しくない人がいる場面では、あえて「飲めない」と言っておいた方が平和に済みます。
無理に自分の本音をさらけ出さず、周囲の雰囲気を大切にできるのは大きな利点です。
しつこい誘いを回避するため
飲み会では、「ちょっとだけならいいじゃん」「乾杯だけでも!」としつこく勧めてくる人がいることも多いです。
本音で断っても「飲まないなんてノリ悪い」と食い下がられるのが面倒なとき、「本当に飲めないんです」と嘘をつけば、それ以上誘われなくなります。
この言い方は、相手の顔も立てつつ、自分の立場も守れるのが大きなメリットです。
無理して飲んで体調を崩すよりも、上手に断ることで自分を守ることにつながります。
「絶対に飲めない」と強調することで、周囲の空気も自然に「無理させてはいけない」と変わります。
体調不良や体質を装うため
本当は飲めるのに「体調が悪い」「昔からアルコールが弱い」などと装うことで、自分の健康を守ることができます。
体質を理由にすると、相手も納得しやすく、無理にお酒を勧めてくることもほぼありません。
さらに「今日だけ調子が悪い」と言えば、毎回同じ理由で断る必要もなく、場面ごとに応用が利きます。
最近はアルコールハラスメントの意識も高まっているため、体質や健康を理由にすることでより断りやすい雰囲気になっています。
自分のペースで飲み会を楽しみたい人には、体質を装うのは有効な手段です。
酔わずに冷静でいたいとき
仕事の付き合いや、大事な会議前の飲み会などでは、酔いたくないと思う場面もありますよね。
「酔うと失言しそう」「トラブルを起こしたくない」と考えている人にとって、嘘をついてお酒を断ることは自分の身を守る方法のひとつです。
酔わずに冷静でいられることで、しっかり会話の内容も覚えていられますし、ビジネスシーンでは信頼を得ることもできます。
また、アルコールが入ると本音が出やすくなり、後悔することもあるので、あえて飲まない選択をする人も増えています。
「今日は控えておきます」とやんわり伝えれば、その場の空気も乱さずに済みます。
自分を守るため
一番のメリットは、何よりも自分自身の身を守れることです。
飲み会では、つい飲みすぎてしまったり、帰り道が心配だったりする場面もあるはずです。
「体質的に飲めない」「薬を飲んでいる」と嘘をついておけば、自分を無理やり追い込むこともありません。
自分の健康やプライベートを守るために、ときには嘘も必要な場面があります。
無理に付き合ってストレスを感じるよりも、自分の心と体を優先する判断は、決して悪いことではありません。
お酒が飲めない理由で嘘をつくデメリット4つ

お酒が飲めない理由で嘘をつくときに考えておきたいデメリットについて、代表的な4つを詳しく解説します。
それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。
信頼を失うリスクがある
お酒が飲めない理由で嘘をつく一番のデメリットは、やはり「信頼関係」に影響を与えるリスクがあることです。
たとえば、普段は「飲めない」と言っているのに、ある日ふとした場面で飲んでいる姿を見られると、「あれ?前は飲めないって言ってたよね」と疑われることがあります。
一度「嘘をついた」と思われると、それまで築いてきた信頼が揺らぐことも。
特に親しい友人や仕事仲間、家族の間では、ちょっとした嘘が大きな亀裂になる場合もあるので注意が必要です。
短期的には波風を立てずに済みますが、長い目で見ると信頼を損なうリスクがあることを頭に入れておきましょう。
バレたときに気まずくなる
「お酒が飲めない」と嘘をついたことが、思いがけないタイミングでバレてしまうと、その場が一気に気まずくなります。
例えば、別の飲み会やSNSなどで飲んでいる写真が回ってきたりすると、周囲から「あれ?」と指摘されることも。
嘘をついたことを咎められたり、必要以上に気を使われたりして、自分自身も落ち込むことがあります。
こういった気まずさを避けるためには、できるだけ一貫した態度を取る必要があります。
たった一度の嘘でも、後々尾を引く場合があるので要注意です。
本当の理由が隠れてしまう
嘘をついてお酒を断ることで、自分が本当に伝えたいことや気持ちが相手に伝わらなくなります。
たとえば「お酒の場が苦手」「アルコールを控えたい」「酔うと不安になる」など、本当の理由がある場合、その思いを伝えられずに終わってしまいます。
その結果、自分自身がストレスを感じたり、誰にも相談できない孤独感につながることも。
また、相手との距離感もなかなか縮まらず、心のモヤモヤが残る原因になります。
お互いの理解を深めたい場面では、なるべく正直な気持ちを伝えた方が関係性も良くなります。
罪悪感を感じることがある
お酒が飲めない理由で嘘をついた後、後ろめたい気持ちや罪悪感を感じる人も少なくありません。
特に親しい人や信頼している相手に嘘をつくと、「自分は正直でいられなかった」と心に引っかかることがあります。
小さな嘘でも、積み重なると自己肯定感が下がったり、気持ちが沈んだりしやすくなります。
場を円滑にするための嘘が、逆に自分自身を苦しめてしまう場合もあるので注意が必要です。
ときには本音で向き合う勇気も大切だということを、心に留めておきましょう。
お酒が飲めない理由で嘘をつくことが許される場面と許されない場面

お酒が飲めない理由で嘘をつくことが許される場面と、逆にあまりおすすめできない場面について解説します。
それぞれのシチュエーションについて、具体的に見ていきましょう。
職場や取引先の飲み会の場合
職場や取引先との飲み会では、「お酒が飲めない」と嘘をついて断ることが比較的許されやすい場面です。
会社の上下関係や取引先のしきたりなど、複雑な人間関係が絡むことが多いため、場の空気を壊さないためにも「体質的に飲めない」「医者に止められている」といった理由が受け入れられやすいです。
とくに、自分の健康や業務に支障が出る場合は、無理せず嘘を活用して自分を守るのも一つの方法と言えるでしょう。
一方で、頻繁に同じメンバーと飲み会がある場合は、毎回同じ理由を使うと不自然に思われることがあるので、注意が必要です。
社会的な関係性を考えながら、うまくバランスを取ることが大切です。
友人同士の集まりの場合
友人同士の飲み会では、「お酒が飲めない」と嘘をつくことが一時的には許される場合もありますが、基本的には本音で話した方が良い関係を築きやすいです。
気心の知れた友人には、自分の気持ちや本当の事情を伝えておくことで、余計な誤解を生まずに済みます。
一方で、付き合いが浅いグループや新しい友人の場合は、最初は無理せず「飲めない」と伝えることで、無理な流れを避けられることもあります。
ただし、何度も嘘をつくとバレやすくなるので、少しずつ本音で接するようにしていくのがおすすめです。
友情を大切にしたいなら、嘘に頼らないほうが後々ラクですよ。
家族やパートナーとの場面
家族やパートナーとの食事やイベントでは、嘘をつくことは基本的に避けた方が良い場面です。
家族や大切な人には、本当の自分を理解してもらうことが信頼関係の土台になります。
とくに健康や生活習慣、将来のことを一緒に考える存在だからこそ、無理に嘘を重ねると後々関係にヒビが入る原因になりかねません。
「今日は飲みたくない」「お酒は苦手」など、率直に気持ちを伝えることで、相手も自然と受け入れてくれることが多いです。
身近な人ほど本音で話し合うことが、信頼を築く一番の近道です。
公式なイベントや祝い事の場合
結婚式や公式なパーティー、目上の方が集まるお祝いの場などでは、「お酒が飲めない」と嘘をつくことは慎重にしたいところです。
どうしても飲みたくない場合は、あらかじめ主催者や幹事に伝えておくのがおすすめです。
宗教上や健康上の理由なら理解されやすいですが、単なる気分やその場しのぎの嘘は、後からバレると印象が悪くなることもあります。
大切な式典やフォーマルな場では、丁寧に断るマナーや配慮が求められます。
社会的な場では、その場の空気や相手の立場を考えた上で、上手に自分の気持ちを伝えていきましょう。
まとめ|お酒が飲めない理由で嘘をつく背景と事情
| ポイント |
|---|
| お酒を断るときの心理 |
| 体質や健康を理由にするケース |
| 職場や飲み会で嘘をつく背景 |
| 人間関係を守るために嘘をつく理由 |
| 健康上の理由を伝える |
| 車を運転する予定があると伝える |
| 薬を服用していると伝える |
| 翌日の予定が早いと伝える |
| 宗教や家庭の事情を理由にする |
お酒が飲めない理由で嘘をつく行為には、さまざまな背景や事情があります。
人間関係や場の空気を大切にしたい、波風を立てたくないという気持ちから、つい「飲めない」と嘘をついてしまう人も多いです。
実際によく使われている断り方には、健康や体質、運転や翌日の予定、宗教や家庭の事情など、さまざまなパターンがあります。
嘘をつくことで気まずさやしつこい誘いを避けられる反面、信頼を失ったり、後で気まずい思いをするリスクもゼロではありません。
大切なのは、自分自身が無理をしすぎないこと、そして本当に信頼したい相手にはできるだけ正直に気持ちを伝えることです。
これからの時代、無理にお酒を飲む必要はありません。
自分のペースを大切にしつつ、上手に断るコミュニケーションを身につけていきましょう。
詳しくは、厚生労働省の「アルコール健康障害対策」や、公式サイトも参考にしてください。