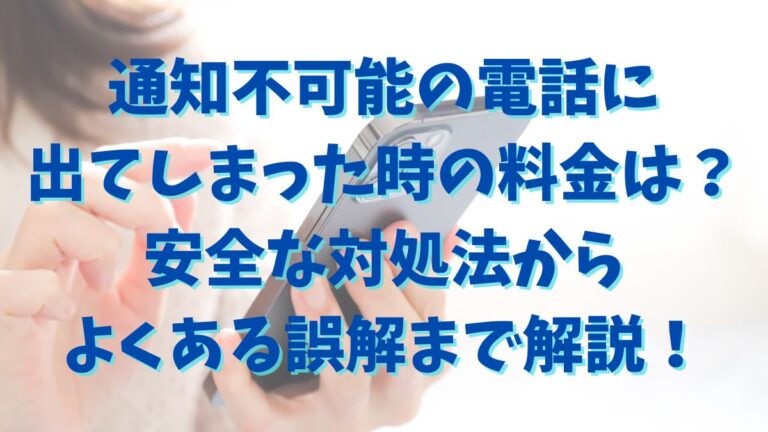スマホに「通知不可能」と表示された電話がかかってきて、うっかり出てしまった。
そんな時、「料金が発生したのでは?」「詐欺電話だったのでは?」と不安になりますよね。
実は、通知不可能の電話に出ても、基本的に料金はかかりません。
ですが、通話後の行動や相手の誘導によっては、思わぬトラブルにつながるケースもあります。
この記事では、「通知不可能」の電話の正体や、出てしまった時に本当に料金が発生するのか、そして安全に対処するための具体的な方法をわかりやすく解説します。
読んだ後には、「もう不安にならない」「次にかかってきても冷静に対応できる」ようになりますよ。
ぜひ最後まで読んで、安心してスマホを使えるようにしてくださいね。
通知不可能の電話に出てしまった時に料金はかかるのか解説

通知不可能の電話に出てしまった時に料金はかかるのかについて解説します。
それでは、詳しく解説していきます。
出ても料金が発生しない理由
結論から言うと、通知不可能の電話に「出るだけ」では料金は発生しません。
通話料は基本的に発信者側が負担する仕組みになっているため、受信しただけではあなたに課金されることはありません。
国内の通信事業者は、受信側に料金を請求するシステムを採用していません。
つまり、着信に出た段階でお金が引かれたり、料金がかかったりすることはないのです。
この点を知っておくだけでも、突然の「通知不可能」という表示に慌てる必要はなくなります。
冷静に対応することが何よりも大切です。
ただし、電話に出た後に「操作を求められた」「番号を押すよう指示された」といった場合は話が別です。
これらの行為を行うと、詐欺の仕掛けに巻き込まれるリスクが出てきます。
「出ても料金は発生しない」という前提をしっかり理解した上で、あとは不要な対応を避けるだけで安全が保たれます。
通話後に料金が発生するケース
電話に出た後の行動によっては、思わぬ形で料金が発生してしまうケースがあります。
代表的なのは「かけ直してしまった場合」です。
特に、相手が国際番号(+から始まる番号)や、プレミアム番号(ナビダイヤル・Q2など)を利用していた場合、こちらから発信することで高額な通話料が課金される仕組みになっています。
また、自動音声で「〇〇にかけ直してください」「番号を押してください」と案内されるパターンも危険です。
案内は、詐欺目的で高額課金回線につなぐ手口のひとつです。
特に国際ワン切り詐欺と呼ばれるケースでは、数秒の通話だけでも数千円の請求が来る場合があります。
発信元の正体が分からない限り、絶対に折り返さないようにしましょう。
このように、「出ただけ」では料金が発生しませんが、「出た後の行動」次第で被害が発生することがあるのです。
国際電話や特殊番号に注意すべき理由
通知不可能と表示される電話の多くは、海外回線を経由しています。
通信網を使うと、発信者番号を正しく認識できないため、「通知不可能」と表示されるのです。
その中には、悪意のある発信者が混じっていることもあります。
特に、国際電話を装って日本人をターゲットにした詐欺が増えています。
中には、音声ガイダンスを使って「確認のために操作を」などと言葉巧みに誘導してくるケースもあります。
また、050や0570などで始まる番号も注意が必要です。
これらはIP電話やナビダイヤルと呼ばれ、接続料金や通話料が通常より高く設定されていることがあります。
「知らない番号」や「見慣れないプレフィックス(番号の頭の数字)」が表示された場合は、即座に切断して問題ありません。
通話料だけでなく、個人情報を盗まれる危険性もあるため、慎重な対応が求められます。
不安な場合は、その番号をインターネットで検索し、同様の報告がないか確認してから判断するのがおすすめです。
知らない番号に折り返してはいけない理由
通知不可能の電話に出てしまっても、折り返す必要は一切ありません。
むしろ、折り返し電話をすることで危険を招く可能性があります。
一番のリスクは「国際課金型詐欺」です。
ワン切りや数秒の通話であなたに「気にならせる」ことが目的で、かけ直した瞬間に高額な通話料が発生します。
また、折り返すことで相手に「この電話番号は実在している」と認識され、迷惑電話リストに登録されてしまうこともあります。
すると、さらに多くの詐欺電話や営業電話がかかってくるようになります。
特に、着信履歴に「+81」「+44」「+63」など海外の国番号が表示されている場合は、絶対に折り返さないようにしてください。
これらは詐欺の多い地域を経由している可能性が高いです。
不安を感じるとつい確認したくなりますが、確認のための折り返しこそが詐欺グループの狙いです。
疑わしい番号は無視が一番安全です。
通知不可能と非通知の違い

通知不可能と非通知の違いを分かりやすく解説します。
この2つの違いを正しく理解することで、不要な不安やトラブルを防ぐことができます。
通知不可能になる仕組み
通知不可能と表示されるのは、発信者の意思ではなく、通信経路上の技術的な制限によって電話番号を表示できない場合に発生します。
たとえば、海外の通信網を経由する国際電話、企業が利用しているIP電話、または一部の公衆電話からの発信が該当します。
この場合、通信機器側で発信者番号を検出できないため、「非通知」ではなく「通知不可能」という表示になるのです。
つまり、発信者がわざと隠しているのではなく、システム的に「番号を通知できない」状態なのです。
非通知設定と混同されやすいですが、この違いを理解しておくと、冷静に判断できます。
技術的な問題に起因するものが多いため、詐欺のように「意図的に隠している」ケースとは区別することが重要です。
非通知設定の意味
非通知設定は、発信者が自分の電話番号を相手に見せたくない場合に「184」をつけて発信する設定のことを指します。
この設定を使うと、受信側には「非通知」または「番号非通知」と表示されます。
つまり、これは発信者の意図によるものであり、通知不可能とは性質が異なります。
非通知設定は、個人のプライバシー保護や匿名での問い合わせに使われることもありますが、一方で悪用されるケースも少なくありません。
特に、営業電話や詐欺、いたずら目的で非通知設定が利用されることもあり、出るべきでない電話の代表例でもあります。
非通知の電話は相手の意思で番号を隠しているという点で、「通知不可能」よりもリスクが高い場合があるのです。
両者の違いと見分け方
通知不可能と非通知は、画面表示で見分けることができます。
一般的には以下のような表示の違いがあります。
| 項目 | 通知不可能 | 非通知 |
|---|---|---|
| 表示内容 | 通知不可能 / 通知不可 | 非通知 / 番号非通知 |
| 発信者の意図 | 意図なし(技術的な問題) | 番号を隠す意図あり |
| 主な発信元 | 国際電話、IP電話、公衆電話 | 個人の電話、詐欺・営業電話 |
| 危険性 | 中程度(折り返し注意) | 高い(応答しない方が安全) |
このように、通知不可能と非通知は根本的な性質が異なります。
どちらも出る必要はありませんが、通知不可能は「相手が番号を出せない状態」、非通知は「相手が番号を隠している状態」と覚えておくと混乱しません。
表示がどちらであっても、不審に感じたら応答しないことが第一です。
特に、夜間や不明な着信が続く場合は、キャリアの拒否設定を活用しましょう。
どちらも危険なケースの見抜き方
通知不可能も非通知も、一見すると harmless に見えますが、悪用されるケースがあります。
その見抜き方を知っておくと安心です。
まず、電話に出た瞬間に「数秒の無音」や「自動音声」が流れる場合は要注意です。
これは、自動発信システムを使った詐欺の可能性があります。
また、何度も時間帯を変えて着信してくる場合は、営業や詐欺グループによる「実在番号の確認」を目的としていることがあります。
この場合、出ると番号がアクティブだと認識され、迷惑電話の対象になります。
さらに、音声で「〇〇の調査です」「あなたの利用状況を確認します」などと話しかけてくる場合も、個人情報を引き出す典型的な手口です。
どんな内容であれ、身に覚えのない相手からの電話に応答しないこと、個人情報を答えないことを徹底すれば、被害を防げます。
通知不可能の電話に出てしまった時の正しい対処法

通知不可能の電話に出てしまった時の正しい対処法を解説します。
間違って出てしまった場合でも、冷静に行動すれば被害は防げます。
まずはすぐに電話を切る
通知不可能の電話に出てしまった場合は、できるだけ早く通話を終了することが大切です。
相手が何を話していても、無言でも、怪しいと感じたら即座に電話を切って構いません。
相手の話を最後まで聞く必要はまったくありません。
中には、自動音声で「あなたの契約状況を確認します」「再手続きをお願いします」などと誘導してくるケースがあります。
これらは詐欺グループがよく使う手口です。
通話を続けてしまうと、相手側にあなたの声を録音され、本人確認の素材として悪用される可能性もあります。
「あれ?怪しいな」と感じた瞬間に通話を切る。これが最も効果的な防御手段です。
絶対に個人情報を話さない
通知不可能の電話では、相手があなたの名前や住所を聞き出そうとしてくるケースがあります。
どんな理由を言われても、個人情報は絶対に話してはいけません。
「あなたの口座情報を確認します」「本人確認のために生年月日を教えてください」などと尋ねられたら、それはほぼ間違いなく詐欺の可能性があります。
特に最近は、カスタマーセンターを装った詐欺が増えています。
口調が丁寧で一見信頼できそうに聞こえても、油断は禁物です。
相手が本当に企業や行政機関であれば、必ず正式な番号から再度かけ直すよう求めてください。
通知不可能のまま連絡してくることはほとんどありません。
「個人情報を話さない」という一点を守るだけでも、被害の大部分を防げます。
不安な時は相談窓口を活用する
もし通話内容が不安だったり、相手が脅すような発言をしてきた場合は、すぐに専門機関に相談してください。
警察相談専用電話「#9110」では、緊急性がないトラブルでも対応してくれます。
架空請求や迷惑電話など、どんな内容でも構いません。
また、消費生活センターの「消費者ホットライン(188)」も頼りになります。
料金請求や詐欺被害など、生活に関する相談を受け付けています。
| 相談先 | 電話番号 | 主な対応内容 |
|---|---|---|
| 警察相談専用電話 | #9110 | 迷惑電話、詐欺、不安な通話の報告 |
| 消費者ホットライン | 188 | 料金トラブル、勧誘、契約被害 |
また、スマホのキャリア(ドコモ、au、ソフトバンク)にも迷惑電話報告の窓口があります。
通話履歴を残しておけば、オペレーターが調査を行ってくれます。
一人で抱え込まず、専門機関の力を借りることが、安心への第一歩です。
通話履歴や内容を記録しておく
通知不可能の電話に出てしまった場合、後から思い出すのが難しくなることもあります。
そのため、通話の時間、内容、相手の話したキーワードをメモしておくことをおすすめします。
この記録は、もし後日トラブルが発生したときに非常に役立ちます。
警察やキャリアに相談する際、より具体的に説明できるためです。
特に、通話直後にSMSやメールが届いた場合は、削除せずに残しておきましょう。
それらが詐欺の証拠として扱われる可能性もあります。
スマホの「着信履歴」「通話録音機能」「スクリーンショット」なども活用し、可能な限り情報を保存しておくと安心です。
「怪しい」と感じた瞬間にメモを取る習慣をつけるだけで、万一の時に自分を守る材料になります。
通知不可能の電話の発信元に多いパターン

通知不可能の電話の発信元に多いパターンを解説します。
通知不可能の表示には、いくつかの明確な原因があります。
これを理解することで、不審な電話に冷静に対応できるようになります。
海外からの国際電話
通知不可能と表示される最も多い原因の一つが、海外からの国際電話です。
海外の通信回線では日本国内の番号通知方式と異なるため、受信側で番号を正しく認識できず、「通知不可能」と表示されることがあります。
特に、英語や聞き慣れない外国語が流れる通話や、自動音声で「サービスの確認」などを促すものは、詐欺の可能性が高いです。
また、海外の通話は一部が「国際プレミアム回線」と呼ばれる高額課金システムを経由しており、こちらから折り返すと数千円以上の料金が発生することもあります。
さらに、国際ワン切り詐欺では、わざと数秒で切ることで「誰だろう?」と興味を引き、かけ直させる手口を使います。
これにより、高額通話料を得るのが目的です。
国際番号(+から始まる番号)や、言語が理解できない通話の場合は、即座に切断するのが最善策です。
一部のIP電話や光電話
次に多いのが、インターネット回線を利用するIP電話や光電話からの発信です。
これらは通信経路の仕様上、番号通知の仕組みが正しく機能しない場合があります。
特に、無料通話アプリや一部の企業のPBX(内線電話)システムから発信される場合、発信者番号を正常に通知できず「通知不可能」と表示されることがあります。
企業によっては、発信専用番号を設定していないため、ユーザーには番号が非表示になる仕組みです。
たとえば、通販会社やサポートセンターからの自動発信などが該当します。
ただし、IP電話の中には詐欺グループが匿名で利用できるものも存在します。
そのため、「企業っぽい内容だったから安心」とは言い切れません。
電話の内容が不明確だった場合は、必ず公式サイトの番号と照合して確認しましょう。
正規の企業であれば、ホームページに正式な連絡先が記載されています。
公衆電話からの発信
意外と知られていませんが、公衆電話からかけられた電話も「通知不可能」と表示されることがあります。
これは、公衆電話自体に固定の番号が割り振られていない、もしくは番号通知機能が有効になっていないためです。
特に、デジタル公衆電話(グレーの筐体で緑色のボタンがあるタイプ)ではこの現象が起こりやすいです。
また、災害時や通信障害の際に一時的に公衆電話から発信された場合にも、「通知不可能」と表示されるケースがあります。
このような電話は危険ではありませんが、内容が不明なまま出るのは避けましょう。
公衆電話を利用する人は減っているため、不自然な時間帯や複数回続く場合は慎重な対応が必要です。
緊急時以外での公衆電話からの着信はほぼ稀なので、無理に応答する必要はありません。
詐欺グループによる架空請求の可能性
「通知不可能」という表示を悪用しているのが、詐欺グループです。
番号を隠すことで相手を油断させ、個人情報や金銭を狙うケースが多く報告されています。
典型的な例は、「料金未納」「サービス停止」「裁判所からの通知」などを装う自動音声通話です。
これらは一見すると公式機関のように聞こえますが、すべて詐欺です。
また、最近はAI音声を使って自然な日本語で話しかけてくるケースも増えています。
声のトーンやイントネーションが人間に近く、気づかないうちに情報を答えてしまう人も少なくありません。
このような電話に出てしまった場合は、すぐに切断し、番号をメモしてからキャリアや警察に報告してください。
放置すると、他の詐欺グループに番号が共有されることもあります。
通知不可能の電話が何度も続く場合、それは偶然ではありません。意図的に狙われている可能性があるため、拒否設定を行うなどの対策が必要です。
通知不可能の電話を防ぐための設定

通知不可能の電話を防ぐための設定について解説します。
通知不可能の電話を完全に防ぐことは難しいですが、いくつかの対策を組み合わせることで、被害のリスクを大幅に減らすことができます。
スマホの設定で拒否する方法
まず最初に行いたいのが、スマートフォン本体で「通知不可能」や「非通知」の着信をブロックする設定です。
多くのスマホには標準で拒否機能が搭載されています。
たとえば、iPhoneでは「設定」→「電話」→「不明な発信者を消音」にチェックを入れることで、登録されていない番号からの着信を自動で無音化できます。
Androidの場合は、電話アプリを開いて「設定」→「ブロック設定」→「非通知・通知不可能をブロック」を選択すればOKです。
これにより、通知不可能の電話は自動的に着信拒否されるか、履歴のみが残る形になります。
仕事などでどうしても出たい場合を除き、基本的には拒否設定を有効にしておくことをおすすめします。
この設定だけでも、迷惑な着信の大部分を防げます。
各キャリアの着信拒否サービスを活用する
スマホ本体の設定に加えて、携帯キャリアが提供している「番号通知お願いサービス」を活用するのも効果的です。
これは、非通知や通知不可能の発信者に対して「番号を通知して再度おかけ直しください」と自動音声で応答するサービスです。
| キャリア | サービス名 | 料金 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 番号通知お願いサービス | 無料 | 自動音声で通知を求める |
| au | 番号通知リクエストサービス | 無料 | 非通知・通知不可能を自動ブロック |
| ソフトバンク | ナンバーブロック | 月額110円 | 個別番号ブロック+非通知拒否 |
| 楽天モバイル | OS標準機能を利用 | 無料 | スマホ設定で拒否可 |
これらのサービスを有効化しておくことで、不審な電話がかかってきても、相手側が番号を通知しない限り通話できなくなります。
キャリアによって設定方法は異なりますが、ショップや公式サイトから簡単に設定可能です。
迷惑電話が続く場合は早めに導入しておきましょう。
迷惑電話対策アプリを導入する
アプリを使った迷惑電話対策も非常に有効です。
最近は、ユーザーからの通報データをもとに詐欺電話を自動で検知してくれるアプリが増えています。
代表的なものには「Whoscall」「迷惑電話ブロック(NTTドコモ公式)」「トビラフォンモバイル」などがあります。
これらをインストールしておけば、着信時に「迷惑電話の可能性あり」と表示してくれます。
また、アプリによっては、データベースをリアルタイムで更新しており、新しい詐欺番号にも即座に対応します。
これにより、通知不可能や非通知以外の不審な電話もブロック可能です。
無料版でも十分役立ちますが、より強力な保護を求めるなら、有料版の導入も検討する価値があります。
設定に不慣れな方でも、アプリのガイドに沿って数分で完了できます。
日常的に不審電話が多い人には特におすすめの方法です。
周囲での注意喚起を広げる
最後に重要なのが、家族や友人など周囲にも注意を呼びかけることです。
特に高齢者やスマホ操作が苦手な人ほど、通知不可能の電話をうっかり取ってしまう傾向があります。
「知らない電話には出ない」「通知不可能は危険」という基本的なルールを共有するだけでも、被害を減らせます。
もし家族に同じような電話が頻繁に来ている場合は、着信拒否設定を一緒に行いましょう。
設定方法を印刷しておくのも効果的です。
また、地域の自治体や警察も、迷惑電話防止のための啓発活動を行っています。
回覧板や地域ニュースなどに情報が掲載される場合もあるため、定期的に確認しておくと安心です。
一人ひとりの意識が高まることで、詐欺グループが活動しにくい環境が自然と作られます。
通知不可能の電話に関するよくある誤解

通知不可能の電話に関するよくある誤解について解説します。
インターネットやSNS上では「通知不可能の電話に出ると料金が取られる」「出るだけで盗聴される」といった情報が拡散されています。
しかし、それらの多くは誤解やデマです。
ここで正しい知識を整理しましょう。
出るだけでお金がかかるは誤解
まず最も多い誤解が、「通知不可能の電話に出ただけで通話料が発生する」というものです。
これは完全な誤解です。
日本の電話回線では、基本的に「発信者課金制」が採用されています。
つまり、発信した側が通話料金を支払う仕組みであり、受信者が料金を負担することはありません。
そのため、通知不可能の電話に出ただけで料金が請求されることはありません。
請求が来るとすれば、それは別の詐欺行為によるものである可能性が高いです。
また、通話後にSMSやメールで「未払いが発生しています」「請求があります」と届いた場合も、絶対にリンクを開かないでください。
これも架空請求詐欺の典型的な手口です。
「出るだけで料金がかかる」は根拠のない噂なので、冷静に対処すれば大丈夫です。
通話しなければ料金は発生しない
次に押さえておきたいのが、「通話をしていなければ料金は発生しない」という事実です。
受信しただけでは課金対象にはなりません。
ただし、相手が「番号を押してください」「確認のためもう一度お話しください」などと誘導してきた場合、操作を行うと有料通話サービスに接続される危険性があります。
特に、「発信者が国際番号(+で始まる)」「自動音声で特定番号への折り返しを求めてくる」などのパターンは要注意です。
これらは国際ワン切り詐欺やプレミアム課金サービスへの誘導の可能性があります。
電話を受けても何も話さず、ボタン操作もしなければ、あなたに料金が発生することはありません。
不安な場合は、契約しているキャリアの通話明細を確認すると安心です。
通話実績がなければ請求されることもありません。
録音や盗聴は基本的に不可能
「通知不可能の電話は録音されている」「スマホを盗聴される」という話もよく見かけますが、これも誤情報です。
通常の電話通話で、相手があなたのスマートフォンを遠隔操作したり、会話以外の音声を録音したりすることはできません。
通話内容は通信会社のシステムを経由して送受信されるため、外部からの不正アクセスは極めて困難です。
ただし、通話中に「特定のアプリをインストールして」と誘導された場合は別です。
アプリを入れてしまうと、マルウェアや遠隔操作ソフトが仕込まれる可能性があります。
つまり、「電話を取っただけで盗聴される」というのは完全なデマですが、「通話後の行動」で危険が生まれることはあります。
不審な発言やアプリ誘導があった場合は、すぐに電話を切り、端末のセキュリティスキャンを実行してください。
不安をあおるSNS情報に注意
最近はSNSや掲示板で、「通知不可能に出たら高額請求が来た」「スマホがハッキングされた」などの投稿が広まっています。
多くは事実確認が取れていない誤情報です。
こうした情報は不安を煽ることで拡散されやすく、結果的に利用者の混乱を招きます。
情報を見つけた場合は、公式機関や通信キャリアのサイトで確認することが大切です。
たとえば、NTTドコモ・au・ソフトバンクの公式FAQには「通知不可能の着信に出ても料金は発生しない」と明記されています。
また、総務省のウェブサイトでも同様の説明があります。
確実な情報源を確認せずに行動することが、最も危険です。
SNSの情報よりも、公式の発表を優先して判断しましょう。
冷静に対応することで、通知不可能の電話に対する不安は確実に軽減できます。
まとめ|通知不可能に出てしまった時の料金と安全対策
通知不可能に出てしまった時の料金と安全対策についてまとめます。
| 対応ポイント |
|---|
| 出ても料金が発生しない理由 |
| 通話後に料金が発生するケース |
| 国際電話や特殊番号に注意すべき理由 |
| 知らない番号に折り返してはいけない理由 |
通知不可能の電話に出ても、基本的に料金は発生しません。発信者課金制の仕組みにより、通話料は相手が負担するからです。
しかし、電話に出た後で「ボタンを押すように言われた」「別の番号にかけ直すよう案内された」といった場合は注意が必要です。
それらは高額課金や詐欺目的の誘導である可能性があります。
不審な電話に出てしまったら、まずはすぐに通話を切り、個人情報を話さないようにしましょう。
もし不安を感じた場合は、警察の「#9110」や消費者ホットライン「188」に相談してください。
また、スマホやキャリアの設定を活用すれば、「通知不可能」や「非通知」の電話を自動的にブロックすることも可能です。
これにより、同じような電話から自分を守れます。
SNS上には誤った情報も多く出回っていますが、公式機関や通信会社の発表を確認すれば、通知不可能の電話を恐れる必要はありません。
冷静に対処し、無視することが最も安全な対応です。
あなた自身が正しい知識を持つことで、詐欺やトラブルからしっかりと身を守ることができます。
参考リンク: