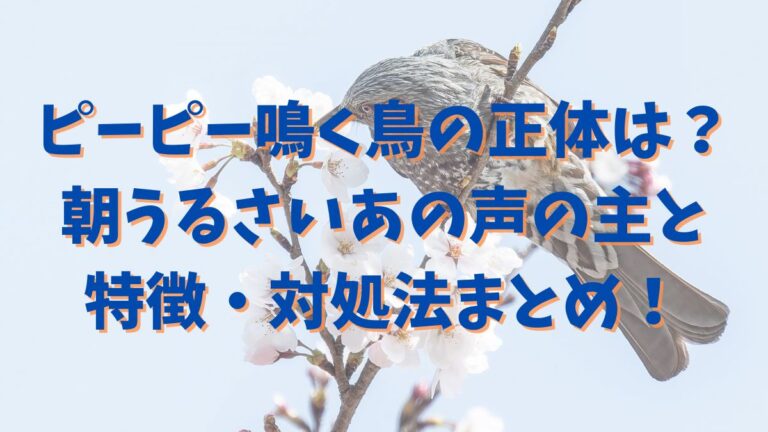「ピーピーって鳴く、あの鳥の名前が気になる…」そんな疑問を持ったことはありませんか?
この記事では、よく聞く高音の鳴き声の正体や、どんな鳥が鳴いているのかを徹底的に解説します。
ヒヨドリやシジュウカラ、エナガなど身近な鳥たちの特徴から、うるさく感じる理由、そして観察のコツや共存のヒントまで、知っておきたい情報が満載。
読めば「うるさい」から「かわいいかも…」に変わるかもしれませんよ。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
ピーピー鳴く鳥の正体とその特徴を徹底解説

ピーピー鳴く鳥の正体とその特徴を徹底解説します。
それでは順番に見ていきましょう!
ヒヨドリの特徴と鳴き声
ピーピーという鳴き声でまず挙がるのが「ヒヨドリ」です。
ヒヨドリはスズメ目ヒヨドリ科に属する中型の鳥で、全長約27〜30cmほどあります。
見た目は灰色っぽく、頭頂部がやや逆立った感じに見えるのが特徴です。
その鳴き声は「ピーピー」「ヒーヨ、ヒーヨ」といった高音で、かなりよく通る声をしています。
特に朝方に大きな声で鳴くため、「目覚まし鳥」と揶揄されることもあるんですよね。
ヒヨドリは日本全国の都市部や山間部でもよく見られる鳥で、人との距離も比較的近いです。
実際、庭先やベランダの植木にやってきたりすることもあり、生活の中でよく出会う鳥のひとつなんです。
果物が大好きで、柿やミカンなどを食べにくる姿を見たことがある人も多いはず。
その行動と鳴き声が印象に残りやすく、「あのうるさい鳥は何!?」と疑問に思う方が多いのも納得です。
シジュウカラの鳴き声のバリエーション
続いて紹介するのは「シジュウカラ」です。
こちらはスズメより少し小さいくらいのサイズで、胸元にネクタイのような黒いラインがあるのが特徴的な可愛い鳥です。
鳴き声は「ツーピー」「チュピチュピ」「ピーピー」など、バリエーションがとても豊富です。
実は、シジュウカラの鳴き声は“言語”に近いとも言われていて、鳴き方に意味があると研究でも話題になりました。
例えば「ピーツピーツ」と鳴いて仲間を呼んだり、「ジジジ」と鳴いて警戒を伝えたりと、場面によって声が変わるんです。
ピーピー鳴く鳥を探している方の中には、このシジュウカラの声に反応して検索している可能性も高いですね。
都市部の公園や郊外の住宅地などにも多く生息していて、人の生活圏とよく重なります。
かわいい見た目とちょこちょこした動きで、バードウォッチャーにも人気の高い鳥なんですよ〜!
エナガの鳴き方と行動パターン
「ピーピー鳴く、しかも小さくて丸い鳥だった」そんな声に該当しやすいのが「エナガ」です。
エナガは体長が13cm程度と、とても小さく、ほぼ尾羽の長さでそのサイズ感を保っています。
そのフォルムはまさに「雪だるま」「ふわふわの団子」みたいな感じで、一目惚れする人続出。
エナガの鳴き声も「チーチー」「ピピピ」「ピーピー」と高音でよく通る音が特徴的です。
群れで移動することが多く、群れ同士で鳴き声を交わしながら飛び回ることが多いです。
ピーピーと高音で、しかも連続的に聞こえるようであれば、エナガである可能性もけっこうあります。
特に寒い時期になるとエナガはより目立ってくる存在です。
都市部でも林や公園の木々の間を飛び交う姿が見られるので、双眼鏡片手に観察してみるのもおすすめですよ。
メジロやスズメなど他の可能性
「ピーピー鳴く」と一口に言っても、他にも該当する鳥はいます。
代表的なのが「メジロ」です。
目の周りの白いリングが可愛いこの鳥も、甲高い声で「チーチー」「ピーピー」と鳴きます。
とても素早く動きながら蜜を吸ったり虫を食べたりしており、庭に梅や椿があるとよくやってきます。
春先には特によく見かける鳥ですね。
そして定番の「スズメ」も、高音で「チュンチュン」と鳴くイメージが強いですが、時に「ピーピー」という風にも聞こえる場合があります。
特に若鳥やヒナが鳴くときにピーピーと聞こえることが多く、それを耳にして検索する方もいます。
見分けるポイントと観察のコツ
では、実際にピーピー鳴く鳥を特定するにはどうしたらいいでしょうか?
まず大事なのは「鳴き声のパターン」をよく聴いてみること。
リズムや高さ、繰り返し方などを記録するだけでも、かなりヒントになります。
次に「時間帯」や「場所」も観察のポイント。
朝早いのか、昼なのか、木の上か地面近くかでも候補が変わってきます。
双眼鏡やスマホの録音機能を使って情報を残し、ネットで調べたりSNSで聞いてみるのもおすすめ。
最近では「鳴き声判定アプリ」などもあるので、それを活用するのもアリです。
観察ってゲーム感覚でできて、けっこう楽しいんですよ。
鳥たちの世界をのぞく第一歩として、ぜひやってみてくださいね。
ピーピー鳴く鳥がうるさいと感じる理由5つ

ピーピー鳴く鳥がうるさいと感じる理由5つについて解説します。
では、それぞれの理由を見ていきましょう。
①高音の鳴き声が耳につきやすい
まず第一に、ピーピーという高音の鳴き声は非常に耳につきやすいんですよ。
人間の耳は高音に敏感なので、ヒヨドリやシジュウカラ、エナガのように高音で鳴く鳥は「うるさい!」と感じやすくなります。
特に静かな環境や早朝、音が反響しやすい場所ではその傾向が強まります。
高音は脳にダイレクトに響くため、不快に感じる人も少なくありません。
これは決して鳥が悪いわけではなく、人間の聴覚の特性によるものなんですね。
「静かな朝にピーピー…」って、目覚まし時計よりキツイこともありますよね(笑)。
②早朝や深夜に鳴くことがある
次に「鳴く時間帯」が問題になるケースも多いです。
特にヒヨドリは朝型の鳥で、日が昇ると同時に鳴き始める習性があります。
これがちょうど人間の睡眠時間とぶつかると、「うるさくて目が覚めた…」ということに。
実際に「朝4時からピーピー鳴かれて寝不足です」なんて悩みをよく耳にします。
また、夏場は日の出が早いので、4時台や5時前から活動を始める鳥もいて、余計に迷惑がられるんですよね。
鳥たちにとっては普通の活動時間でも、人間にとっては深夜レベルですもんね〜。
③集団で鳴くため騒がしく感じる
鳥が一羽で鳴いているだけならまだしも、多くの場合は「群れ」で鳴いています。
シジュウカラやエナガは特に群れで移動しながらコミュニケーションを取るので、あちこちから鳴き声が聞こえてくるんです。
それが「ピーピーピーピー…」と連続して聞こえると、まるで騒音のように感じることも。
しかも、鳥たちはそれぞれ少しずつ違う声で鳴くので、音が重なって「ザワザワ」感が増して聞こえます。
いわば「自然の合唱団」ですが、住民にとってはやや迷惑な演奏会になることも…。
「なんか外がずっとうるさい…」と感じたら、群れの鳥が原因かもしれません。
④住宅地との距離が近い
近年は自然と都市部の境界があいまいになりつつあり、住宅地に鳥が普通に入ってくるようになっています。
特にヒヨドリやスズメは都市適応力が高く、庭やベランダにもやってくるほど。
そうなると、人の生活空間と鳥の生活空間が重なり、鳴き声が直で届いてしまうんです。
窓を閉めても聞こえてくるほどの声量の鳥もいて、特に木が近くにあるお宅では鳴き声が反響して大きく感じることもあります。
「すぐそこにいるじゃん…」ってくらい近いと、さすがに気になりますよね。
自然と共存してる証とはいえ、毎朝続くとストレスになることもありますよね〜。
⑤鳥の数が年々増えている可能性
最後に注目したいのが「鳥の個体数の増加」です。
都市部の緑地や公園が整備されたこと、農薬の使用が減ったことなどにより、一部の鳥の生息数が増えているという報告もあります。
特にヒヨドリやムクドリは都市部に適応しやすく、年々目撃例が増加していると言われています。
個体数が増えれば当然、鳴き声の量も増えていきます。
1羽がうるさかったのが、今では5羽10羽と鳴き出す…そんな環境の変化が起きているんですね。
「昔はこんなにうるさくなかったのに」なんて声が出るのも納得です。
ピーピー鳴く鳥を特定するための観察方法
ピーピー鳴く鳥を特定するための観察方法についてご紹介します。
「なんの鳥だろう?」と気になったら、ぜひ以下の方法を試してみてくださいね。
時間帯と鳴き方の傾向を記録する
鳥を特定するうえでまず大事なのは、「いつ、どこで、どんな風に鳴いていたか」を記録することです。
たとえば「毎朝6時ごろ」「木の上で」「ピーピー3回鳴いて止まる」といった具体的なパターンが分かれば、それだけでかなり絞り込みが可能です。
鳥は種類によって活動時間や鳴き方が違うので、時間帯や鳴き声のリズムはかなりのヒントになります。
さらに季節や天候、周囲の環境(住宅街、公園、山間部など)もメモしておくと、より正確に特定できます。
スマホのメモ機能やボイスレコーダーなどを使えば、すぐに記録できて便利ですよ!
「また鳴いてるな〜」で終わらせず、ちょっと記録しておくだけで世界が広がりますよ♪
鳴き声アプリや図鑑を活用する
最近は便利な時代で、鳥の鳴き声を聞かせるとAIが判別してくれるアプリがいくつも出ています。
たとえば「バードネット」「Merlin Bird ID(コーネル大学開発)」などは、スマホのマイクを通して鳥の声を解析してくれます。
日本語対応しているものや、使いやすさに定評のあるアプリも増えているので、まずは無料で試してみるのがおすすめです。
また、紙の図鑑も根強い人気があります。
鳴き声付きの音声図鑑や、QRコードで鳴き声が聞ける書籍などもあり、視覚と聴覚の両方からアプローチできるのが魅力です。
「アプリでサッと調べて、図鑑でじっくり確認」っていう組み合わせも良い感じですよ〜!
双眼鏡で姿形を確認する
鳴き声だけではどうしても分からないときは、姿を見てみるのが一番手っ取り早い方法です。
双眼鏡を使うことで、遠くの枝にいる鳥や、すばしっこく動く小鳥でもしっかり観察できます。
ポイントは「色」「大きさ」「模様」「しっぽの長さ」などをしっかり見ること。
鳴き声と一緒に「見た目」もセットで記録できれば、ほぼ特定できるといっても過言ではありません。
最近では初心者向けの軽量コンパクトな双眼鏡も多く、価格も1万円以下からあるので、気軽にチャレンジできます。
「これが鳴いてたのか〜!」と姿を確認できた瞬間、感動しますよ〜!
録音してSNSや専門サイトで相談する
どうしても自力で特定できない場合は、鳥好きの人たちに聞いてみるのもひとつの手です。
スマホで鳴き声を録音して、Twitter(X)やInstagram、noteなどにアップし、「この声の鳥は何ですか?」と聞いてみると、驚くほど親切に教えてくれる方がいます。
また、「日本野鳥の会」や「バードリサーチ」などの専門機関のWebサイトにも、鳥の名前や鳴き声を投稿して特定を手伝ってもらえるフォームがあることもあります。
こういった知識のシェアは、鳥好きの方々にとっては楽しいコミュニケーションのひとつなんですよ。
録音の際はなるべく周囲の音を減らして、クリアに録れるようにすると正確性もアップします。
「みんなに聞いてみる」って、実は一番確実で早い方法かもしれませんね!
ピーピー鳴く鳥がもたらす自然のメリット

ピーピー鳴く鳥がもたらす自然のメリットについて解説していきます。
うるさいと感じがちなピーピー鳴く鳥たちも、実は自然界ではとっても大切な存在なんですよ。
害虫の駆除に貢献してくれる
鳥たちは、日々の食事の中でたくさんの昆虫や幼虫を食べています。
特にシジュウカラやエナガなどの小型の鳥は、毛虫やアブラムシ、ガなど、庭や畑の天敵をモリモリ食べてくれるんです。
つまり、彼らは「天然の害虫ハンター」なんですね。
農薬を使わずに植物を守りたいという家庭菜園の人やガーデニング好きな方にとっては、実はすごくありがたい存在なんです。
ピーピー鳴いてる=パトロール中って思うと、ちょっと好感度上がりませんか?
「うるさいけど、頼れるやつらなんだな〜」と思ってもらえたら嬉しいです!
植物の受粉や種まきに役立つ
鳥たちは、花の蜜を吸ったり、果実を食べたりしているうちに自然と「受粉」や「種まき」の役割を果たしています。
たとえば、メジロは花の蜜を好む鳥で、梅や椿などに集まることで花粉を運び、受粉を助けています。
また、ヒヨドリやムクドリが果実を食べると、消化後に種を排出し、その場所で新しい植物が育つきっかけにもなるんです。
これってまるで「森の配達屋さん」みたいな働きですよね。
そう考えると、鳥たちの活動ってただの「鳴き声」以上に、自然界に大きな影響を与えているんですよ。
ピーピー鳴いてるのは、次の花や木を育てるための準備中なのかも…って思ってもらえると素敵です!
自然観察の楽しさを教えてくれる
ピーピーと鳴く声が聞こえると、「どんな鳥だろう?」って気になりませんか?
そこから双眼鏡で探したり、スマホで調べたりしていくと、まるで宝探しのようなワクワクした気持ちになるんです。
実際に、バードウォッチングをきっかけに自然観察を始めた人はとても多いんですよ。
家の周りにいながら自然と触れ合えるって、実はすごく贅沢な体験ですよね。
子どもと一緒に観察すれば、学びの時間にもなりますし、親子のコミュニケーションにもなります。
「うるさい!」を「おっ、今日は誰が鳴いてるかな?」に変えられたら、毎日がちょっと豊かになりますよ♪
環境のバロメーターになる存在
鳥たちは環境の変化にとても敏感です。
そのため、鳥の種類や数が変わってくると、「この地域の自然環境に変化が起きている」サインとも捉えられます。
たとえば、「以前は聞こえなかった鳥の鳴き声が聞こえるようになった」というのは、緑が増えた証かもしれません。
逆に、「最近全然鳴き声がしない」というのは、何か環境に悪い影響が出ている可能性もあります。
つまり、鳥たちは「生きた環境センサー」なんですね。
鳴き声を耳にしたとき、ちょっとだけ立ち止まって「この声があるということは…」と自然に思いを巡らせてみるのもおすすめです。
ピーピー鳴く鳥への対処法と共存のヒント
ピーピー鳴く鳥への対処法と共存のヒントについて紹介します。
鳥の声が気になって仕方ない…そんなときに役立つヒントをお伝えしますね。
鳴き声が気になるときの対処法
「朝からピーピーうるさい!」と感じたとき、まずはカーテンや窓の対策をしてみましょう。
二重サッシにすることで、鳴き声をかなりシャットアウトできますし、遮音カーテンを使うのも効果的です。
寝室の窓の方向を変える、ベッドの位置をずらすなどの工夫でもだいぶ変わってきます。
また、耳栓やホワイトノイズのアプリを活用して睡眠を妨げられないようにするのもおすすめ。
一時的にでも、朝のストレスを減らす手段を持っておくとかなり楽になりますよ。
「完全に音を消す」は難しくても、「うまく付き合う」って大事なポイントです!
鳥を傷つけずに遠ざける方法
「できれば近くに来ないでほしい」…そう思うこともありますよね。
そんな時に使えるのが、鳥を傷つけずに遠ざける方法です。
たとえば、ベランダや庭先にキラキラしたもの(CD、反射テープ、アルミホイルなど)を吊るすと、光の反射を嫌って近寄らなくなります。
風で動くもの、例えば風車や回転式のオブジェなども効果があります。
ただし、鳥も学習するので、同じ場所に同じものを置きっぱなしにすると慣れてしまうことも。
位置やアイテムを定期的に変えていくのがコツです。
「追い払う」じゃなくて「来にくくする」ってイメージのほうがやさしくて良いですよね♪
巣作りを防ぐための工夫
ピーピー鳴いてるなと思ったら、いつの間にか巣を作られていた!なんてこともあります。
一度巣を作られると、鳥は法律で守られているため、勝手に撤去できないケースが多いんです。
だからこそ、あらかじめ「巣作りさせない」工夫が大切になります。
エアコンの室外機の裏や軒下、ベランダのすみなど、よく巣を作られる場所には、ネットや防鳥テープで物理的にアクセスできないようにしましょう。
とくに春から初夏は巣作りシーズンなので、早め早めの対策がポイントです。
「かわいいけど、ここはごめんね〜」の気持ちで対策してみてくださいね。
共存のために心がけたいこと
ピーピー鳴く鳥は、うるさいと感じる一方で、自然界の中で大きな役割を果たしています。
完全に排除しようとするより、「適度な距離感で共存する」ことを意識すると、お互いにストレスも減ってきます。
たとえば、庭に餌台を設置して「このエリアでは歓迎」「こっちには来ないでね」とゾーンを分けてあげる方法もあります。
また、子どもたちや家族と一緒に鳥を観察する時間を設けることで、「うるさい」から「面白い」に変わることも。
自然と触れ合う時間って、意外と心を落ち着けてくれるんですよ。
「ちょっとうるさいけど、なんか愛おしいかも…」と思えるような距離感を目指していきましょう♪
まとめ|ピーピー鳴く鳥の正体と自然との付き合い方
| 鳴き声の特徴と対応方法 |
|---|
| ヒヨドリの特徴と鳴き声 |
| シジュウカラの鳴き声のバリエーション |
| エナガの鳴き方と行動パターン |
| メジロやスズメなど他の可能性 |
| 見分けるポイントと観察のコツ |
この記事では、「ピーピー」と高音で鳴く鳥たちの正体を紹介し、それぞれの特徴や見分け方、自然界での役割まで詳しく解説しました。
うるさいと感じる鳴き声も、見方を変えると自然とのつながりを感じる貴重なサイン。
ヒヨドリやシジュウカラ、エナガなど、私たちの身近にいる鳥たちは、虫を食べたり植物の受粉を助けたりと、知られざる「いい仕事」をしているんです。
今後は鳴き声が気になったとき、ちょっと立ち止まって空を見上げてみてください。
自然と共に暮らす日常の中に、少しだけやさしい気持ちが芽生えるかもしれませんよ。
さらに詳しく知りたい方は、以下の参考リンクもどうぞ。