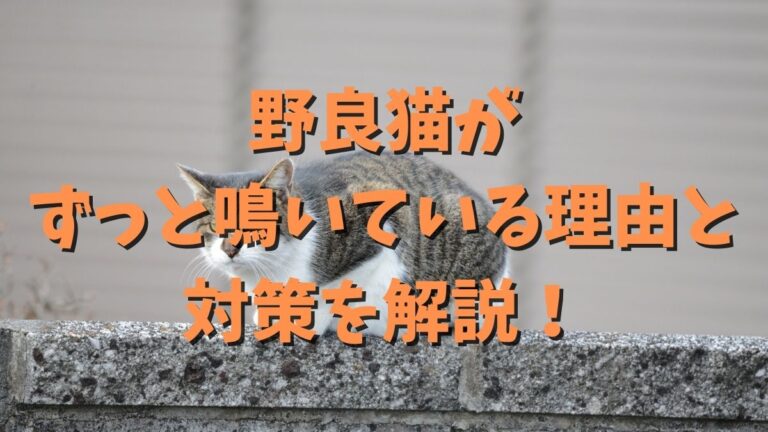街中や住宅街で、ずっと鳴いている野良猫を見かけることがあります。
その姿を見ると、何か困っているのではないか、助けが必要なのではないかと気になることもあるでしょう。
なぜ野良猫は鳴き続けるのでしょうか?
その理由と対策について解説していきます。
野良猫がずっと鳴いている理由は?

発情期
野良猫が特に大きな声で鳴くのは、発情期によるものが多いです。
猫の繁殖期は春と秋がピークですが、環境によっては一年を通して発情することもあります。
都市部や暖かい地域では発情期が長引く傾向があり、頻繁に鳴き声が聞こえることがあります。
オス猫はメス猫を、メス猫はオス猫を呼ぶために、大きな声で遠くまで響くように鳴く場合があります。
また、複数のオス猫がメス猫をめぐって争う際にも、大きな鳴き声を発することがあり、それが夜中にも続くことが多いです。
子猫や仲間を呼んでいる
母猫は子猫を呼ぶときや危険を察知したときに独特な鳴き声を発します。
その鳴き声は短く鋭いことが多く、子猫に対する指示や警告の役割を果たします。
また、仲間とコミュニケーションを取るために鳴くこともあり、特に群れで行動する野良猫の間では重要なサインとなります。
特に子猫が母猫を探して鳴くことが多く、母猫はそれに応えることで安心させ、無事を確認するのです。
お腹が空いている
飢えた野良猫は食べ物を求めて鳴き続けることがあります。
子猫や高齢の猫は、自力で食料を見つけるのが難しく、助けを求めるように鳴くことが多いです。
人に助けを求めることもあり、餌を与えると鳴き止むケースもありますが、無闇にエサを与えると野良猫問題が深刻化する可能性があります。
そのため、地域のルールを守りつつ、適切な方法で支援することが重要です。
病気の可能性
猫が異常に鳴く場合、病気の可能性も考えられます。
高齢の猫は認知症による異常行動として鳴くことがあり、昼夜を問わず無意味に鳴き続けることもあります。
怪我や病気の際にも痛みを訴えるように鳴くことがあり、特に内臓疾患や関節炎のような慢性的な痛みを伴う病気では、頻繁に鳴く傾向が見られます。
ストレスや不安による神経症的な鳴き声もあるため、猫の行動と併せて注意深く観察することが重要です。
鳴き声の特徴
「アオーン」と鳴く場合
猫が「アオーン」と鳴く場合、発情期や警戒の意味を持つことが多いです。
オス猫がメス猫に対して鳴く際によく見られます。
この鳴き声は遠くまで響く特徴があり、求愛のサインとしてだけでなく、他のオス猫に対する牽制の意味を持つこともあります。
また、警戒している場合には声のトーンがやや異なり、低く長めの鳴き声になる傾向があります。
「シャー」や「ウー」と鳴く場合
威嚇の際は「シャー」や「ウー」といった低い声で鳴きます。
これは敵を追い払うためのもので、体を大きく見せながら鳴くことが特徴です。
耳を後ろに伏せたり、尻尾を膨らませたりするなどのボディランゲージを伴うことが多く、無理に近づくと攻撃される可能性があるため注意が必要です。
興奮状態の猫は爪を立てて飛びかかることもあるため、威嚇のサインを見たら慎重に距離を取ることが重要です。
対策と保護方法

動物病院での受診
明らかに衰弱している猫や、怪我をしている猫を見つけた場合は、動物病院へ連れて行くことが推奨されます。
骨折や感染症などが疑われる場合は、迅速な対応が求められます。
野良猫の場合は警戒心が強いため、無理に捕まえようとしないことが重要です。
安全に捕獲するためには、キャリーケースやタオルを活用し、驚かせないように慎重に接近することが望ましいでしょう。
去勢・避妊手術がもたらす効果
野良猫の増加を防ぐためには、去勢・避妊手術が有効です。
地域猫活動として手術を施し、元の場所に戻す「TNR活動(Trap-Neuter-Return)」が推奨されており、これにより猫の繁殖が抑制され、鳴き声の減少にもつながります。
TNR活動を通じて猫たちが健康を維持しやすくなるほか、地域住民とのトラブルも軽減されるため、より持続可能な共存が可能になります。
また、手術を受けた猫は縄張り意識が弱まり、攻撃的な行動が減少するため、他の猫との争いも減る傾向があります。
まとめ
野良猫がずっと鳴いている理由は、発情期や仲間とのコミュニケーション、空腹、病気などさまざまです。
その影響は人間の生活にも関わるため、適切な対策が求められます。
特に深夜の鳴き声は住民のストレスとなることもあり、地域全体での取り組みが必要です。
地域で協力しながらTNR活動を進めたり、動物病院での受診を検討することで、野良猫との共存を目指すことが大切です。
猫の行動や鳴き声のパターンを理解し、適切な対応をすることで、人と猫が快適に共生できる環境を整えることが可能になります。
本記事がみなさまの生活にお役に立つと幸いです。