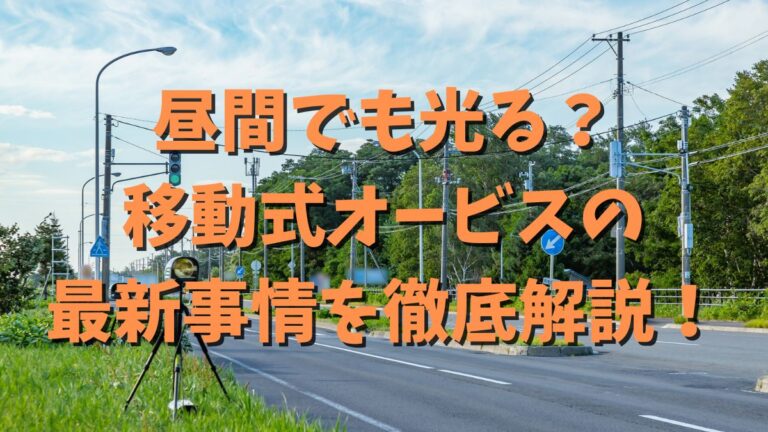最近、街中や住宅街でもよく見かけるようになった「移動式オービス」。
「え?こんな場所で取り締まりやってるの?」「昼間なのにオービスが光ったような…?」
そんな経験、ありませんか?
従来の固定式オービスとは違い、移動式オービスは突然現れてドライバーの油断を突いてきます。
しかも、最近では昼間でも気づかないほど静かに、そして正確に記録を残す機種も増えており、いつの間にか違反通知が届いてしまうというケースも。
本記事では、「移動式オービスは昼間でも光るのか?」という疑問をはじめ、安全運転のためのポイントまで、やさしく解説していきます。
これを読めば、知らない間に違反していた…なんて事態を防ぐための知識が身につきますよ!
移動式オービスの仕組みとは?

従来の固定式オービスとの違い
移動式オービスとは、文字通り「移動可能な速度違反自動取り締まり装置」のことです。
従来のオービスといえば、高速道路や幹線道路の高架などにがっちりと設置された「固定式」を思い浮かべる方も多いでしょう。
ですが、移動式オービスはその名の通り、車載型や三脚型で自由に設置場所を変更できるのが最大の特徴です。
固定式は一度設置すると基本的に場所を移動することはなく、ドライバーも場所を覚えて減速するなど回避行動をとりやすいですが、移動式は日によって場所が変わるため、事前に把握するのが難しくなっています。
これはドライバーに常に安全運転を促すという意味でも、非常に有効な仕組みと言えるでしょう。
また、固定式は大型で目立つ上、事前に警告看板も設置されています。
一方、移動式は非常にコンパクトで目立ちにくく、警告看板が設置されないケースも増えています。そのため「まさかここで?」というような場所で突然撮影されてしまうということもありえます。
つまり、移動式オービスは、ドライバーの不意を突くかたちで取り締まりを行うことができ、実際に「速度超過の温床」となっている生活道路や通学路などでの事故防止にもつながっているのです。
どうやって速度を測定しているのか
移動式オービスが速度を測定する方法はいくつかありますが、主に「レーダー方式」や「レーザー方式」が採用されています。
レーダー方式では、装置から電波を発射し、車両に当たって跳ね返ってくる電波を解析することで速度を算出します。
一方、レーザー方式ではより精密な測定が可能で、誤差も少なく、近年導入が進んでいる方式です。
とくに最近は「LSM-310」や「MSSS」などの小型で高性能な移動式オービスが注目されています。
これらは、通過する車の速度を瞬時に判定し、違反があればその場で自動撮影します。
速度が一定の基準を超えると、ナンバープレートや車両の写真が記録され、ドライバーには後日「出頭要請」や「通知書」が送られるという流れです。
技術の進化により、昼夜問わず高精度な取り締まりが可能になっており、特に夜間に強い赤外線カメラなども搭載されているため、ドライバーが気づかないうちに違反が記録されているというケースも増えています。
どこに設置されるの?ランダム性のポイント
移動式オービスの強みは、なんといってもその“自由な設置場所”です。主に以下のような場所に設置されることが多いです。
-
通学路や生活道路
-
住宅街周辺
-
工事中の道路
-
幹線道路の交差点付近
-
見通しの悪いカーブや下り坂
これらの場所には共通して「事故が起きやすい」「速度超過しやすい」「注意が必要なエリア」という特徴があります。
警察は日々の事故統計や地域住民からの要望などをもとに、取り締まり場所を決定しています。
つまり、毎回同じ場所に設置されるわけではなく、日によって、また時間帯によっても変わるため、ドライバーにとっては非常に予測が難しい存在です。
「今日はここに設置してあったけど、明日は違う場所かも」といった具合で、まさに“神出鬼没”な存在。
これにより、ドライバーが日頃から安全運転を意識するようになることを狙っているのです。
小型・軽量化された最新モデル
移動式オービスは年々進化しており、今では片手で持てるほどのサイズまで小型化されています。
たとえば、有名な「LSM-310」などは、三脚に乗せるだけで簡単に設置でき、車載型としても使える優れモノです。
小型化が意味するのは、設置・撤去が簡単で、少人数の警察官でも運用できるということです。
これにより、警察側も効率よく広範囲に取り締まりを行えるようになりました。
また、軽量なので車のトランクにも収まるため、パトカーや警察車両に常時積んでおき、必要に応じて設置するといった柔軟な運用も可能となっています。
コンパクトながらも精度の高いカメラやセンサーを搭載しており、暗い場所や天候の悪い日でも正確に違反を捉えることができます。
つまり、見た目に騙されてはいけません。小さくても、しっかりと“見ています”。
音も光もない?静かに記録される事実
移動式オービスのもう一つの特徴は、「静かに」取り締まりを行うことです。
従来の固定式オービスでは、光がパッと光ったり、シャッター音が鳴ったりと「記録された」ことが分かるケースが多かったですが、移動式はその点が違います。
レーザー式の機種では、撮影の際にフラッシュが全く見えない場合もあり、ドライバーは自分が撮影されたかどうか気づかないことがほとんどです。
これは赤外線を用いたカメラや、光量を自動調整するシステムのおかげです。
結果的に「光らなかった=大丈夫」と思っていると、後日通知書が届いて驚くことになるかもしれません。
実際に、SNSでも「気づかなかったのに通知が来た」という声が多く見られます。
つまり、音も光もなく「サイレント」で記録されるのが今の移動式オービスなのです。気づかなかったからと言って安心してはいけません。
昼間でも光る?移動式オービスの実態

昼間でも光るのか?
「移動式オービスは光るの?」という疑問は、多くのドライバーが抱えているものです。
特に昼間に走行中、「光ってないから大丈夫だったかな?」と気になる方も多いでしょう。
結論から言うと、昼間でも移動式オービスは光ることがあります。ただし、すべての機種がそうとは限りません。
固定式オービスの多くは撮影時に赤いフラッシュを発光させますが、移動式オービスではその仕様がまちまちです。
最近の移動式オービスは赤外線や高感度カメラを使っており、フラッシュなしでも鮮明に撮影が可能になっています。そのため、昼間でも違反があれば記録されますし、フラッシュが見えなくても油断は禁物です。
また、光るタイプでも昼間の太陽光にかき消されて、運転中の目では気づきにくいこともあります。実際には「うっすら光った気がするけど見間違いかも」と思ったら、後日通知が来て初めて気づくケースも。
逆に、しっかり光るタイプであっても見逃すことはあるということです。
つまり、「光った=撮られた」「光らなかった=セーフ」という単純な判断はできないのが現代の移動式オービスの特徴です。
昼間はフラッシュが分かりにくくなりやすいため、何も感じなかったからと言って安心してはいけません。
フラッシュが見えなかったらセーフ?
結論から言うと、フラッシュが見えなくても違反は記録されている可能性があります。
移動式オービスには赤外線カメラを搭載した機種があり、これは暗闇でも鮮明に車両を撮影できる優れた性能を持っています。
日中であればなおさら、フラッシュの力を借りずとも、明るい光の中で高解像度の撮影が可能です。
中にはドライバーの表情まで分かるほどの鮮明な画像が撮られているケースもあります。
つまり、フラッシュは「撮影のサイン」ではなく、ただの補助光です。
フラッシュがない=記録されていない、というのは大きな誤解です。
また、最近ではLEDタイプのフラッシュもあり、昼間の太陽光のもとでは目に見えにくいこともあります。
サングラスやフロントガラスの反射でさらに見逃しやすくなるため、よほど注視していないと気づきにくいのです。
さらに、最新型の移動式オービスは撮影が「静音」で、光や音でドライバーに気づかれないように設計されています。
つまり、違反時の「撮られたかも?」という不安を逆手にとり、抑止力を高めているのです。
運転中にフラッシュが見えなかったからといって安心せず、安全運転を心がけることが一番の対策です。
光らないオービスも存在する理由
「移動式オービスには光らないタイプもある」と聞くと不安になりますが、これは事実です。
赤外線式カメラを搭載している機種は、撮影時にまったくフラッシュを使用しないケースもあります。
その理由は主に2つあります。
1つは、夜間でも周囲に配慮するためです。たとえば住宅街や通学路などでの取り締まり時に強いフラッシュが光ると、住民や歩行者に驚きを与えてしまうことがあります。
そういった影響を避けるため、赤外線カメラで「気づかれずに」撮影を行う方式が採用されています。
もう1つは、違反者に気づかせずに取り締まるためです。違反した瞬間に「光った!やばい!」と気づかれると、次から注意されてしまう可能性があります。
それよりも、撮られたことに気づかず後日通知が届くことで、ドライバーに「え、いつの間に…」という驚きと反省を促すことが目的です。
つまり、光らないこと自体が“戦略”なのです。
フラッシュで威嚇する時代から、静かに確実に取り締まる時代へと進化しているというわけですね。
もちろん、すべての移動式オービスが光らないわけではありませんが、「光らないオービスもある」と知っておくことで、より一層の注意を払った運転ができるようになるはずです。
撮影時の仕組みと光の強さの関係
移動式オービスの撮影時には、車のナンバーや前面の様子を正確に記録する必要があります。
そのため、必要に応じて補助光としてフラッシュ(赤色LEDやキセノンライトなど)を使う場合もあります。
ただし、近年のオービスは技術の進化により「強い光を使わなくても綺麗に撮れる」性能を備えているのです。
昼間は自然光があるため、フラッシュの必要性がそもそも低く、光の強さは時間帯や周囲の明るさに応じて自動で調整されるタイプもあります。
夜間はしっかり光らせる一方で、昼間はほとんど光らないか、ドライバーからは気づけない程度のフラッシュしか使わないよう設計されています。
また、フラッシュの「点灯タイミング」も瞬間的で、0.1秒未満の短い時間で終わるため、注意していないとまったく気づかないまま通過してしまうこともあります。
つまり、フラッシュの光が見えにくいからといって「撮られていない」とは限らないのです。
むしろ、撮影にフラッシュが必須ではない時代に入っているとも言えるでしょう。
このように、撮影時の光はあくまで「補助」的なもの。カメラの性能が上がったことで、静かに、しかも確実に証拠を残せるようになっているのです。
実際の取り締まり映像や証言からわかること
YouTubeやSNS、掲示板などでは、実際に移動式オービスに遭遇した人の投稿が多く見られます。
中でもよくあるのが、「気づかなかったけど通知が来た」「光った気がしたけど見間違いだと思ってた」という証言です。
ある投稿者は、「昼間、郊外の国道を走っていたとき、三脚に乗った箱のような機械があったけど気にも留めなかった。
数日後、警察から通知が来て初めて移動式オービスだったと知った」と語っています。
実際、オービスはカモフラージュされていたり、警察官が遠くから監視していたりして、違反者に気づかせないように工夫されています。
また、ドラレコ映像でも、光が確認できないにも関わらず撮影されていたという例もあります。
こうした情報は、移動式オービスが静かに、しかし確実に取り締まりを行っている証拠です。
ネット上ではリアルタイムで設置情報を共有するアプリやSNSも活用されていますが、完全に回避するのは難しい状況です。
結局のところ、最も確実な対策は「違反しないこと」に尽きます。
捕まったらどうなる?オービスでの違反処理の流れ

オービスに撮影された後の通知方法
移動式オービスに速度違反を記録された場合、その場で警察官に止められることは基本的にありません。
固定式と同様、移動式オービスも「非接触式」の取り締まりなので、撮影後に写真やデータを元に違反処理が行われます。
撮影された情報は、ナンバープレートや車両の前面、そして運転手の顔写真などが含まれており、それらをもとに「車両の所有者」に対して数日〜数週間以内に『出頭通知書』や『呼出状』が郵送されます。
この封筒は多くの場合、警察署または公安委員会から送られ、中には以下のような書類が入っています。
-
出頭要請通知(いつ・どこで・何キロオーバーだったかの記載)
-
必要書類の案内(免許証など)
-
出頭場所(最寄りの警察署など)
ここで重要なのは、通知が「運転者本人」ではなく「車の所有者」に届くということです。
レンタカーや社用車の場合は、所有会社を通じて使用者に伝達されることもあります。
なお、軽微な違反(たとえば15km/h未満の速度超過)であれば、「反則金納付書」のみが届くケースもあり、出頭不要で済む場合もあります。
つまり、移動式オービスで撮影されたら、ほとんどの場合“何もされないまま終わる”ということはまずないと考えておいたほうがよいでしょう。
出頭命令の有無と流れ
オービスに記録された速度超過の内容によって、通知内容は異なります。
たとえば軽微な違反の場合は反則金だけで済む「青切符」扱いになることもありますが、速度超過が大きい場合や、再犯で悪質と判断された場合は出頭命令が届きます。
出頭命令が届いたら、指定された日時に最寄りの警察署や交通課に出向きます。
そこで以下のような流れで処理が行われます。
-
違反内容の説明(場所・日時・速度など)
-
撮影写真の提示(ナンバーや顔写真で本人確認)
-
事実確認(運転者が本人かどうか)
-
供述書の記入(違反内容に対するコメントや署名)
-
処分内容の説明(点数・反則金・出頭後の流れ)
ここで本人ではないと主張する場合には、別の運転者の情報提供を求められる場合もあります。
ただし、嘘の供述をしたり、責任転嫁を試みた場合には、刑事責任が問われる可能性もあるため、正直に対応することが重要です。
また、出頭命令を無視した場合、警察から再通知が来るか、最悪の場合「逮捕令状」が発行されることもありますので、絶対に放置してはいけません。
点数と反則金の目安一覧
速度違反に対する行政処分は、超過したスピードに応じて点数と反則金が決められています。
以下に代表的な速度超過の処分内容を表でまとめます。
| 速度超過(一般道) | 点数 | 反則金(普通車) |
|---|---|---|
| 15km/h未満 | 1点 | 9,000円 |
| 15〜19km/h | 1点 | 12,000円 |
| 20〜24km/h | 2点 | 15,000円 |
| 25〜29km/h | 3点 | 18,000円 |
| 30〜49km/h | 6点 | 刑事処分(赤切符) |
| 50km/h以上 | 12点 | 刑事処分(免許取消の可能性) |
※高速道路では処分内容がやや異なります。
特に30km/h以上の速度違反になると、「赤切符」が切られ、行政処分に加えて刑事処分(罰金または略式裁判)が科されるケースが多くなります。
また、累積点数により、免停や免許取消のリスクも高まります。
つまり、たった1回の速度違反が免許の命運を分けることもあるということです。
免停になるスピードの目安
速度違反で免許停止処分になる基準は「累積点数」と「違反の種類」によって決まります。では、どれくらいのスピードを出すと免停になる可能性があるのでしょうか?
一般的な基準としては以下の通りです。
-
30km/h以上の速度超過(一般道):6点
-
50km/h以上の速度超過:12点(免許取消の可能性)
例えば、違反歴がなくてもいきなり30km/h以上オーバーすると、それだけで6点加算されて30日間の免許停止処分になります。
過去に違反歴がある人が15〜20km/hオーバーをしてしまうと、累積点数により免停ラインを超える可能性があります。
再犯(短期間での繰り返し違反)や悪質なケース(深夜・学校周辺などでの違反)は、通常よりも重い処分が下されることがあります。
つまり、「少しくらいオーバーしても大丈夫だろう」という油断が命取りになる可能性があるということです。
免許停止になれば、通勤・通学・仕事など日常生活に大きな支障をきたすことは間違いありません。
異議申し立ては可能?その方法とは
もし自分が「移動式オービスに記録されたが心当たりがない」「運転していたのは自分ではない」といった場合、異議申し立て(弁明)は可能です。
ただし、これは簡単ではありません。
警察や公安委員会が証拠とするのは、「ナンバープレート」「運転者の顔」「違反時刻と場所の記録」などです。
これらの情報に間違いや不備がある場合、出頭時や後日の手続きの際にその旨を伝えることができます。
主な異議申し立ての方法は以下の通りです。
-
出頭時に「自分ではない」と申し立てる
-
供述書に異議を明記する
-
弁護士を通じて反論書を提出する
-
写真に写っている人物が他人である証拠を提出
ただし、オービスは高性能なカメラで顔までしっかり撮影しているため、言い逃れは難しい場合が多いです。
逆に、虚偽の申告をしてしまうと「虚偽供述罪」に問われる可能性もあるため、正確で誠実な対応が求められます。
もし本当に心当たりがない場合や、車が盗まれていた・貸していたなどの事情がある場合は、弁護士に相談することが最善の方法です。
安全運転のために知っておくべきこと

速度違反のリスクと実際の事故件数
速度違反は、単なる「ルール違反」にとどまらず、重大な交通事故の原因にもなります。特に死亡事故に関しては、速度超過が直接的な要因になっているケースが多く、警察庁の統計によれば、交通死亡事故の約30%以上が速度超過に起因しています。
たとえば、たった時速10kmのオーバーでも、ブレーキの制動距離は数メートル単位で長くなります。これは、歩行者や自転車と衝突する可能性が高まるだけでなく、自分自身の命をも危険にさらすということです。
また、速度が上がれば上がるほど、事故時の衝撃は指数関数的に増加します。時速30kmでの衝突は「高所からの転落」、時速50kmでは「建物から飛び降りたレベル」、そして時速80km以上では「即死レベルの衝撃」とも言われます。
加えて、速度超過は他の違反との複合になることも多く、信号無視や追越し違反などが絡むことで、さらに事故のリスクが高まります。実際に、速度違反による死亡事故の多くが「複数の違反行為」を同時に行っていたことが明らかになっています。
つまり、「ちょっと急いでいるから」「少しならバレないだろう」という軽い気持ちの速度超過が、取り返しのつかない事故を引き起こす可能性があるということです。
違反せずに済む運転習慣
速度違反を防ぐには、日頃からの運転習慣が何よりも大切です。
以下のようなポイントを意識するだけで、違反を未然に防ぐことができます。
-
制限速度の確認を習慣にする
信号待ちの時や走行中に標識をこまめにチェックすることで、自然と意識が高まります。 -
流れに乗りすぎない
他の車が速いからといって自分もスピードを出してしまうのは危険です。マイペースを守りましょう。 -
運転前に余裕を持つ
急いでいる時ほどスピードを出しがちなので、5〜10分早めに出発するよう心がけると安心です。 -
エコドライブを意識する
燃費の良い運転はスピード抑制にもつながります。緩やかな加速・減速を意識しましょう。 -
休憩をしっかり取る
疲れていると集中力が低下し、スピード感覚が鈍くなりがちです。長距離ではこまめな休憩が大切です。
これらの行動は一見地味に見えますが、事故防止にもつながり、結果的に自分や他人の命を守ることに直結します。
安全運転は「意識」ではなく「習慣」にすることが最も効果的です。
速度制限の意味を理解しよう
道路に設定されている制限速度には、すべて明確な理由があります。
単に「ゆっくり走らせるため」ではなく、その場所の構造や交通量、周辺環境(学校・住宅街・カーブなど)を考慮して、最も安全とされる速度が決められているのです。
たとえば、住宅街で30km/hに制限されているのは、急に子どもや自転車が飛び出してきたときに対応できるようにするためです。
また、山道などで40km/hや50km/hに設定されているのは、急カーブや滑りやすい路面での事故防止のためです。
高速道路でも、制限速度が100km/hから80km/hに下がっている区間は、風の影響や勾配の関係で事故が起こりやすいためです。
つまり、制限速度はその道の「安全の目安」なのです。
そのため、無理に「速く走ることが正しい」と思い込まず、その道ごとに「なぜこの速度なのか」を考えることが大切です。
そうすることで、自然と注意深い運転になり、結果として違反も避けられるようになります。
移動式オービスの導入目的
移動式オービスが全国的に導入されている理由は、単に取り締まり強化のためではありません。
最大の目的は、交通事故の抑止と安全意識の向上です。
従来の固定式オービスでは、設置場所が限られており、「ここを過ぎればスピードを出しても大丈夫」といった形で意味を成さなくなるケースも多くありました。
移動式オービスは、それを打破するための「いつどこで取り締まりが行われているかわからない緊張感」をドライバーに与えるツールです。
特に、生活道路や通学路などの「これまでノーマークだった場所」にも設置可能なため、地域住民の安全を守るためにも有効な手段です。
また、現場の警察官が柔軟に取り締まりを行えるため、事故発生直後の重点対策にも迅速に対応できます。
つまり、移動式オービスは「違反を取り締まるため」ではなく、「違反を未然に防ぐため」に使われているのです。
そのことを理解すれば、取り締まりを「怖いもの」としてではなく、「安全運転のサポーター」として捉えることができるはずです。
最終的に守るのは自分と大切な人の命
どんなに制度や機器が進化しても、最後に事故を防げるのは、運転者一人ひとりの意識だけです。
速度違反がもたらすリスクは、自分だけでなく、家族・友人・通行人など、周囲の人たちの命にも直接関わる問題です。
「たった1回の違反が、人生を変えてしまう」
これは決して大げさな話ではありません。
例えば、スピードを出した結果、人をはねてしまった場合、刑事責任だけでなく、民事上の賠償責任、そして社会的な信用や家族の生活にも大きな影響が及びます。
逆に言えば、安全運転を心がけるだけで、それらのリスクを大きく減らせるのです。
子どもの送り迎え、買い物、通勤、旅行。日常の運転すべてが、大切な人との時間を守る行動であると考えれば、スピードを出す理由はどこにもないと感じられるはずです。
移動式オービスは、そんな意識を日常に呼び戻してくれる大切な「注意喚起装置」として、今後ますます役割を強めていくでしょう。
まとめ
移動式オービスは、これまでの固定式とは違い、場所を自由に移動できることから「いつ・どこで取り締まりが行われているか分からない」という緊張感をもたらします。
昼間であっても光らず静かに撮影される最新機種が増えているため、ドライバーが気づかないうちに違反を記録されるケースが後を絶ちません。
結局のところ、最も確実な対策は「日頃からの安全運転」に尽きます。
移動式オービスに怯えるよりも、違反をしない運転スタイルを身につけることが、事故防止・違反回避の近道です。
運転とは、移動手段であると同時に、自分と大切な人の命を守る行為でもあります。
ぜひこの記事をきっかけに、速度や運転習慣について一度立ち止まって考えてみてください。